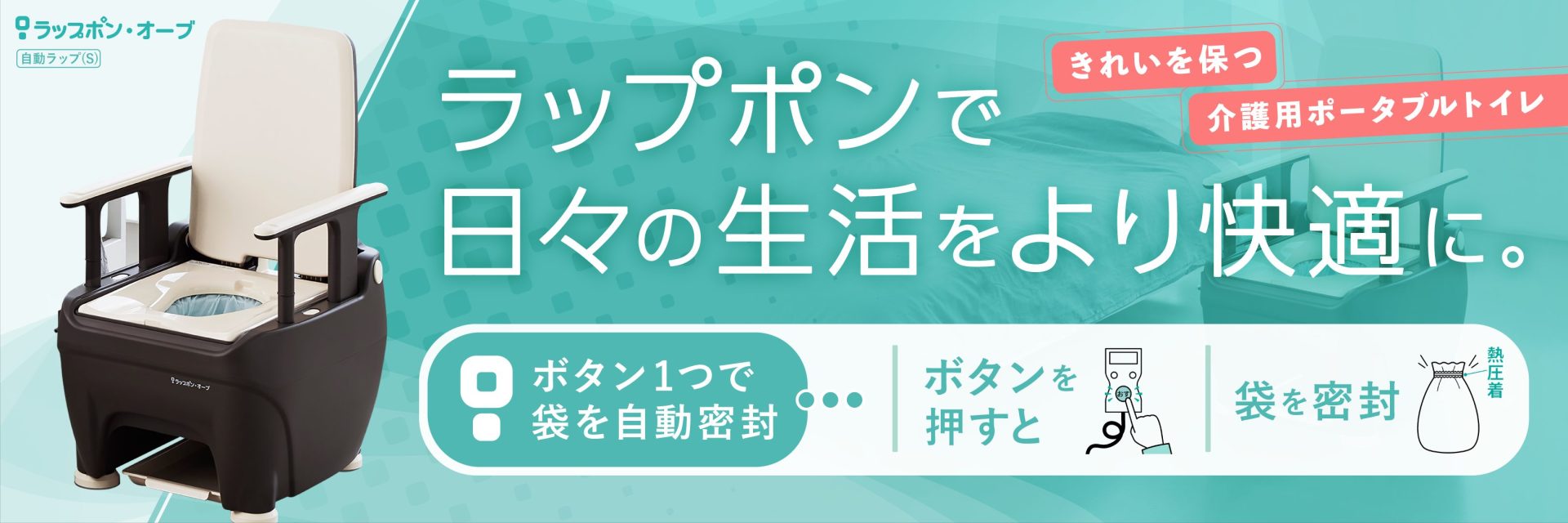家族が介護を必要とする状態になった時、「何から始めたらいい?」「どこに相談すべきか分からない」と、漠然とした不安を感じる方は少なくありません。このような時に、介護分野の専門家として利用者・家族の心強い味方になってくれるのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。
この記事では、ケアマネジャーの担っている役割を紹介するとともに、相談できることや活用ポイントまで、介護初心者の方にも分かりやすく解説します。
Contents
ケアマネジャーとは
ケアマネジャーは、高齢者や家族の抱える介護問題に関する相談に応じて、その方がどのような介護サービスを必要とするのか判断し、ケアプランを立てて、必要に応じて支援機関と連絡・調整を行う専門職です。
都道府県の認定する公的資格の一つで、高齢者福祉施設や居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどに勤務しています。
ケアマネジャーの仕事内容は多岐にわたり(後述)、利用者に対して介護保険サービスが滞りなく提供され、地域での充実した暮らしが継続できるよう支援する役割が期待されています。
ケアマネジャーの4つの役割
ケアマネジャーが担う役割は大きく分けて4つあります。以下、一つずつ整理して説明します。
介護分野における相談援助職
ケアマネジャーは介護分野における相談援助職として、介護を必要とする高齢者・家族の相談に応じるとともに、抱えている課題解決のために介護保険サービスを紹介したり、適切な支援を提供してくれる機関を紹介する役割を担っています。
ケアプランの作成と見直し
ケアマネジャーは要介護高齢者のケアプランを作成し、必要に応じてその内容を見直す役割を担っています。
要介護認定において、要支援・要介護と判定された方が介護サービスを利用するために、
ケアマネジャーはその方たちの希望に応じて、適切な介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、作成されたケアプランに基づいて滞りなくサービスが提供されているか、提供されている
サービス品質に問題がないかなどをチェック(モニタリング)し、必要に応じてサービスの種類、
内容、頻度などを見直します。
介護保険サービス事業者等との連絡・調整
介護サービスが滞りなく利用者に提供されるように、サービス提供事業所や、病院、役所の窓口などと連絡・調整を行います。
また、利用者の心身状況が変化しモニタリングを行った結果、ケアプランの内容に変更が出た場合には、利用者や家族、サービス提供事業者との連絡・調整を行ったうえで見直し、介護サービスの品質の維持を図る役割を担っています。
要介護認定の申請代行、更新支援
ケアマネジャーは、利用者の要介護認定の申請を代行したり、更新を支援します。
要介護認定の申請や手続きは、本人が行うことを原則としていますが、何らかの事情(例:関節リウマチで文字が書けない、足腰が悪く市町村窓口へ行くことができないなど)で申請ができない場合は、
居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに所属するケアマネジャーに代理申請や手続きの代行を
依頼することができます。要介護区分の更新に係る申請等の事務処理についても同様です。
相談に関する費用
ケアマネジャーへの相談は、無料で行うことができます。
費用は、全て介護保険で賄われ、利用者・家族の自己負担は一切ありません。
また、先述のケアプラン作成や、要介護認定の代行なども同様で、全て無料です。
どのような相談ができる?
ここからは、実際にケアマネジャーに寄せられる相談内容の例を紹介します。
介護保険サービスに関する相談
- 要介護認定を受けたい、申請したい。
- 要支援1と判定された。利用できる介護サービスを知りたい。
- 家族を老人ホームに入所させたいが、どのように手続きを行えば良いか分からない。
- 有料老人ホームに興味があるが、家の近くにたくさんあって選べない。相談にのってほしい。
健康や生活に関する相談
- 歳を取っても元気で健康でいるための運動をやってみたい。
- 脳トレなどをやって認知症を予防したい。
- 外出の機会を増やし、適度に人との関わりを持ちたい。
- 最近、関節の動く範囲がせまくなってきたので、体を動かして身体機能の維持を図りたい。
介護の負担軽減に関する相談
- 体調が悪くなり、家族を介護できそうにない。一時的に施設へ入所させられないか。
- 自宅での介護が長期化して、身体的・精神的に参っている。何とか解決方法がないか知りたい。
医療・医療機関に関する相談
- 家族が物忘れが多くなり、認知症かもしれない。物忘れ外来、認知症外来のある病院を紹介してほしい。
- 要介護認定をしたいが、主治医(かかりつけ医)がいない。診てくれる医療機関を紹介してほしい。
住宅改修や福祉用具に関する相談
- 自宅での生活を続けるために、屋内外の段差を解消したい。
- 利用できる、または購入できる福祉用具の種類を知りたい。
- お布団で寝るのが不便なので、介護用ベッドを利用したい。介護保険でレンタルできるか知りたい。
- お箸で食事することが難しくなったので、自助具を利用したい。
経済的な支援・制度に関する相談
- 生活に困窮しており、一時的にお金を借りられる制度について知りたい。
- 経済的に困窮しており、安価で入居できる老人ホームを探してほしい。
- 認知症になった時に備えて、あらかじめ資産管理の方法を決めておきたい。
- 医療費がかさんで経済的負担が大きい。負担を軽減する制度がないか知りたい。
- 介護保険サービスの利用が多く、経済的な負担が大きい。費用負担を軽減する制度について知りたい。
ケアマネジャーへの相談の流れ
ここからは、ケアマネジャーへ相談する流れを紹介します。
| 順 | 項目 | 内容 |
| 1 | 市役所に相談する | 要介護認定をしたいのでケアマネジャーを紹介してほしいと伝える。 |
| 2 | ケアマネジャーと支援機関が紹介される | 地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所の一覧が示される。 一覧のなかから、自身の希望する機関・ケアマネジャーを選ぶ。 選べなければ、市役所から紹介を受ける。 |
| 3 | ケアマネジャーへ連絡する | 選んだ、または紹介されたケアマネジャーへ連絡し、 面談を希望する旨を伝える。 |
| 4 | ケアマネジャーとの面談 | 該当する地域包括支援センター、または居宅介護支援事業所へ足を運び、担当のケアマネジャーと面談を行う。 上記機関へ行くことが難しければ、電話で相談し、自宅等で来訪してくれるよう依頼することも可能。 |
| 5 | 抱えている問題の明確化 | ケアマネジャーに対し、困っていること、解決してほしいことを伝えて 問題の明確化を図る。 |
| 6 | 介護保険サービスの利用に向けて動き出す。 | ケアマネジャーの支援を受けて、要介護認定の申請を行い、 訪問調査などを経て要介護区分が判定される。 判定区分に応じて、介護保険サービスの利用が開始される。 |
ケアマネジャーを上手に活用するポイント
ここからは、ケアマネジャーを上手に活用するポイントを紹介します。
ケアマネジャーの活用は、介護サービスの充実や、生活の質的向上にも繋がりますので、
ここで紹介したポイントを実践してみてください。
心身状況、住宅環境などを伝える
現在の心身状況や、住宅環境を詳しく伝えましょう。具体的には次の情報を共有すると良いでしょう。
- 認知症や物忘れはあるのか。あるのなら、いつ頃から始まったか。
- 身体のどの部位が不自由か。原因は何か。
- 屋内での移動で不便な場所はどこか。転倒の危険があるか。
- 既往歴(病気にかかった履歴)や服薬の状況
- 最近、体調の変化や環境の変化はあったか など
希望する生活や困ったことを伝える
自身の希望する生活像や、日常生活上で困っていることを伝えると良いでしょう。
具体的には次の情報を共有すると良いです。
- 家族による介護について、かけられる時間や負担の度合い
- このような生活を送りたいなどの将来の希望
- 生活を送るうえでどのような時に困るのか、何ができて、何ができないのか
- 経済状況(経済的に困っているか) など
疑問や不安は遠慮なく質問する
介護に関する疑問や不安があれば、遠慮なく質問して解消しましょう。
利用者・家族側から積極的に質問し、どのような点に疑問や不安を抱えているのか、
置かれた状況について情報を共有することが重要です。
質問の例は次のとおりです。
- このサービスは、具体的にどのようなことをしてくれるのか。
- このサービスを利用した場合、費用負担はどれくらいか。
- 今後の流れが分からないので、説明してほしい。
- 利用者、または家族がしなければならないことは何か。 など
信頼関係を築いて気軽に相談できる間柄になる
ケアマネジャーと積極的なコミュニケーションを図ることで、信頼関係を築き、気軽に相談できる間柄になることを目指すことが重要です。
そのためには、次のことを心がけると良いです。
定期的な連絡
体調や状況に変化があった場合には、積極的に連絡し、情報を共有しましょう。
感謝と敬意を示す
介護サービス事業者との連絡・調整は手間のかかる仕事です。その仕事に対して感謝と敬意を示し、
引き続き十分に支援してくれるよう依頼しましょう。
不満や問題点を伝える場合は感情的にならない
提供される介護サービスに問題があったとして、ケアマネジャーに苦情を言う場合も、
感情的にはならずに冷静に伝え、建設的に問題が解決するように情報交換しましょう。
「○○だったらもっと良い」や「○○なので困っています」など具体的な事柄を伝え、
「共に解決を目指す」というスタンスが好ましいです。
まとめ
今回の記事では、ケアマネジャーがどのような役割を担い、どのような相談に応じ、
どのように介護生活をサポートしてくれるのかを詳しく解説してきました。
ケアマネジャーは、利用者・家族の立場に立って、抱えている課題の解決を目指してケアマネジメントをしてくれる専門職です。
介護保険制度は仕組みが複雑で、その活用や手続きを家族だけで行うには限界があります。
今後の生活の質にも関わる重要なことだからこそ、まずは介護の専門家であるケアマネジャーを頼ってください。
この記事を読んで「相談してみようと」と思ったら、お住まいの自治体や、居宅介護支援事業所、
地域包括支援センターのいずれかへ連絡してみてください。
無料で相談に応じてくれるので、この記事で紹介したケアマネジャーの活用ポイントを踏まえて、
相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
参考文献
- 「介護支援専門員(ケアマネジャー)」厚生労働省
- 「ケアマネジメントに係る現状・課題」厚生労働省 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会
- 「ケアマネジャーのしごとガイド」WAM NET 独立行政法人福祉医療機構