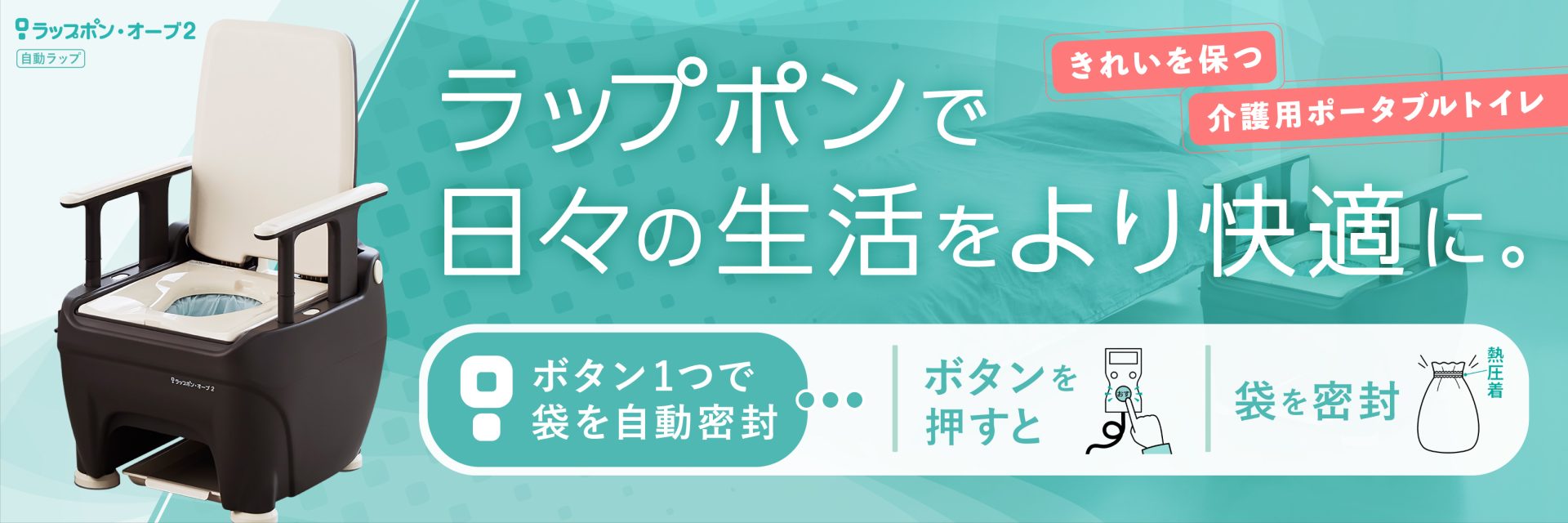家族が介護を必要とする状態になった時、「何から始めればいい?」「どこに相談したら良いか分からない」と、漠然とした不安を感じる方は少なくありません。
そのような時に心強い味方になってくれるのが、高齢者介護の相談窓口である地域包括支援センターです。
この記事では、地域包括支援センターがどのような役割を持ち、どのような方が利用できるのか、具体的な相談内容の例などについて分かりやすく解説します。
家族が介護を必要とする状態になった時、「何から始めればいい?」「どこに相談したら良いか分からない」と、漠然とした不安を感じる方は少なくありません。そのような時に心強い味方になってくれるのが、高齢者介護の相談窓口である地域包括支援センターです。
この記事では、地域包括支援センターがどのような役割を持ち、どのような方が利用できるのか、具体的な相談内容の例などについて分かりやすく解説します。
Contents
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターとは、市町村が設置主体となり、住民が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、無料で介護・医療・福祉などの相談に応じるとともに、必要な支援・援助につなげてくれる機関です。
同センターは、市町村が直営するものもあれば、社会福祉法人や社会福祉協議会、医療法人などが委託を受けて運営するものもあります。おおむね、中学校区ごとに設置され、後述する各種相談に応じるとともに、要介護認定の申請窓口としての機能を持っています。
センターには保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等が配置(後述)され、それぞれの専門性を発揮しながら、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために様々な支援を行います。
高齢者や家族、地域住民の生活・福祉をあらゆる面からサポートしてくれる、まさに、地域の相談窓口と言えます。
居宅介護支援事業所との違い
介護について調べていると「居宅介護支援事業所」という言葉も目にするでしょう。両者の違いを理解しておくことで、適切な相談先を選べます。
地域包括支援センターは高齢者やその家族、地域住民など幅広い人が相談に訪れることができ、地域全体の高齢者支援を担当します。一方、居宅介護支援事業所は主に要介護1〜5の方を対象とし、具体的なケアプランの作成や介護サービス事業所の紹介などを専門に行います。
つまり、介護が必要になった初期段階や、どこに相談すればよいか分からない段階では地域包括支援センターへ、すでに要介護認定を受けていて具体的なサービス利用を検討する段階では居宅介護支援事業所へ相談するのが一般的です。地域包括支援センターから適切な事業所を紹介してもらうこともできます。
地域包括支援センターの4つの役割
地域包括支援センターは、主要な4つの事業を通して地域住民の福祉を向上させる役割を担っています。それぞれが、どのような内容なのか詳しく説明します。
生活や介護に関する総合相談(総合相談支援事業)
地域包括支援センターは、生活や介護に関することだけでなく、医療、健康、住まいに関する相談を幅広く受け付けています。そのうえで、高齢者・家族の抱える悩みを聞き、様々な制度やネットワークを活用して、適切な支援制度やサービスへ繋げてくれます。
上記以外でも「要介護認定の申請をしたい」「どこに相談したら良いか分からない」、「そもそも、相談して良い内容か分からない」といった些細な相談も受け付けてくれるので、困ったことがあれば、まずは地域包括支援センターに連絡することをおすすめします。
介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)
介護予防ケアマネジメントとは、地域に住む高齢者が要介護状態にならないように、健康づくりや介護予防を支援する事業です。
高齢者や家族の相談に応じるなかで、その方の心身状況や希望を踏まえたうえで、健康的な生活の送り方や、サービスの利用に関する助言・紹介をしています。
また、要介護認定で要支援1・2と判定された方が、加齢や病気によって心身が悪化しないように、介護予防を目的としたケアプラン(介護予防サービス・支援計画書)を立案します。
権利擁護事業
権利擁護事業とは、高齢者が本来持つ権利や財産を守るための取り組みです。
高齢者のなかには、自身が認知症になって財産管理や契約行為が難しくなったり、家族から虐待を受けていて人権が侵害されていたり、特殊詐欺や悪徳商法によって被害に遭ったりしている人もいます。
地域包括支援センターでは、このような方たちの権利が侵害されることがないよう、成年後見制度の紹介・活用促進や、高齢者虐待の予防・早期発見、悪質商法や詐欺の被害を防ぐ取り組みを行っています。
包括的・継続的ケアマネジメント支援
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業とは、地域の医療・福祉機関が緊密に情報共有・連携できるよう、ネットワークを構築したり、連携の質的向上を図ったりする取り組みです。
高齢者が住み慣れた地域で生活していくためには、必要なサービスが適切に利用できるよう、地域全体でその環境・体制を整えていなければなりません。
そこで、地域包括支援センターが中心となって、地域で活躍する介護支援専門員(以下、ケアマネジャー)の指導・支援を行うとともに、医療機関や支援機関とミーティングを行って意見交換し、必要に応じて連携が取れる体制を整えています。
地域包括支援センターの相談事例
実際にどのような相談が寄せられているのか、具体例を見てみましょう。
相談事例1:介護保険の申請について
「母が最近足腰が弱くなり、買い物に困っている。介護保険を使いたいがどうすればよいか」という相談。センターで申請手続きの説明を受け、認定調査まで案内してもらえます。
相談事例2:認知症の疑い
「父の物忘れがひどくなり、同じことを何度も聞いてくる。どうすればよいか」という相談。かかりつけ医への受診を勧められたり、必要に応じて認知症専門医の紹介をしてくれます。また、家族の接し方についてのアドバイスも受けられます。
相談事例3:退院後の生活不安
「入院していた母が退院するが、自宅での生活が心配。どんな準備が必要か」という相談。退院前から介入し、必要なサービスや福祉用具の手配を支援します。
相談事例4:交友関係について
「父が定年退職後、家に引きこもりがちで心配。同年代の友達をつくる機会がほしい」という相談。地域の体操教室、趣味のサークル、サロン活動など、地域で開催されている様々な交流の場を紹介してもらえます。社会参加を促すことで、介護予防にもつながります。
相談事例5:介護と仕事の両立
「仕事をしながら親の介護ができるか不安」という相談。デイサービスなどの利用で介護負担を軽減する方法を提案してもらえます。
事例以外にも高齢者福祉に関する幅広い悩みごとを相談することができるため、悩みや不安があれば、一度地域包括支援センターに相談してみてください。
対応してくれる専門職
地域包括支援センターに勤務し、活躍する専門職を紹介します。それぞれの専門職がどのような役割を担っているのか説明します。
保健師(看護師)
地域包括支援センターの保健師は、主に次の役割を担っています。
- 各種相談の対応
- 要支援状態の悪化防止に役立つ取り組み
- 要支援1・2の方の介護予防ケアプラン作成
- 心身の健康維持の取り組み など
社会福祉士
地域包括支援センターの社会福祉士は、主に次の役割を担っています。
- 各種相談の対応
- 高齢者虐待の防止、早期発見の取り組み
- 成年後見制度の啓発、利用促進
- 特殊詐欺などの予防啓発活動
- その他の権利擁護事業 など
主任ケアマネジャー
地域包括支援センターの主任ケアマネジャーは、主に次の役割を担っています。
- 各種相談の対応
- 地域におけるネットワーク力を高めるための取り組み
- 地域で活躍するケアマネジャーの支援、助言
- ケアマネジャーが抱える支援困難ケースへの指導、助言 など
利用対象者
地域包括支援センターの主な利用対象は、センターが設置されている地域に住む65歳以上の高齢者とその家族です。要介護認定を受けているかどうかは問われていません。
また、地域で活躍するケアマネジャーなど、介護・福祉、医療分野で活躍する専門職も同センターを利用できます。気軽に問い合わせて助言を得たり、情報交換したりすることができます。
費用・相談方法
地域包括支援センターは、全国どこのセンターでも無料で利用できるので安心です。直接、地域包括支援センターを訪問して相談することもできますが、電話相談をすることも可能です。
地域包括支援センターの利用方法
地域包括支援センターは、おおむね中学校区に1つが設置されており、どのセンターがどこの地域を担当するかは、あらかじめ市町村が決めています。
初めて利用する場合は、まずは自治体の担当窓口へ連絡し、自分の住む地域を担当する地域包括支援センターに関する情報を得ましょう。
その後、該当するセンターへ電話連絡し、相談の予約を取ると良いでしょう。緊急の場合は、予約がない状態でもセンターへ足を運んでみましょう。
地域包括支援センターは初めての相談先として最適
インターネット上では「地域包括支援センターでは期待していた効果が得られなかった」という声も見られます。しかし、その評判は本当に正しいのでしょうか?
地域包括支援センターは直接的な介護サービスの提供などをする場所ではなく、あくまで支援や相談・紹介などがメインです。
実際の要介護認定や介護サービスを受けるためには、支援者が実際に連絡するなど行動が必要になることがあります。
そのため、本来の役割を超えた対応を期待していた方にとっては、「期待していたサービスが受けられなかった」と感じることがあるのは事実です。
しかし、センターの役割を正しく理解した上で利用すれば、介護を始める上で非常に心強い存在となります。役立つポイントとしては下記の3つがあります。
初めての相談先として最適
介護保険制度は複雑で、初めての方には分かりにくいものです。地域包括支援センターは、そのような方々の「最初の一歩」をサポートする役割を担っています。何から始めればよいか分からない段階でも、丁寧に道筋を示してくれます。
地域資源とのつながり
地域の医療機関、介護事業所などとのネットワークを持っているため、個人では知り得ない情報やサービスを紹介してもらえます。この「つなぐ力」こそが、センターの大きな強みです。
公的機関としての安心感
民間事業所と異なり、営利目的ではない公的機関です。特定の事業所に偏らない中立的な立場から助言が受けられるため、初めて介護に向き合う方にとって安心できる相談先と言えます。
介護での悩みは一人で解決することは難しく、専門家に相談することが大切です。地域包括支援センター以外にも、市区町村の福祉課、居宅支援事業所、社会福祉協議会など相談できる場は多くあります。
介護に関して悩みや不安がある場合は、ぜひ専門家や公的機関に相談をしてみてください。
よくある質問
相談したら必ず介護サービスを受けなければならない?
いいえ、必ずしも介護サービスを利用する必要はありません。相談内容に応じて、保健師や主任ケアマネジャーが、必要な情報提供や助言、適切な支援機関の紹介を行いますが、介護サービスの利用は必須ではありません。
相談内容や個人情報は守られる?
はい、相談内容や個人情報は守られますので安心して相談できます。相談内容によっては「人に知られたくない」「相談したこと自体、他者に知られたくない」という場合もあるかもしれませんが、専門職が相談内容に関して、他者に漏らすことはありませんし、個人情報も適切な形で秘匿されるので安心です。
要介護認定の申請や手続きをしてもらえるか?
はい、要介護認定の申請や手続きを代行することも可能です。申請が億劫な方や、介護保険の内容がよく分からない方は、気軽に相談してみましょう。
また、主治医・かかりつけ医がいない場合でも、相談に応じてもらえます。場合によっては、新たに医療機関を受診して、主治医となる医師を決めるまでのプロセスまでサポートしてくれます。
センターへ行くことが難しい場合はどうしたらいい?
事情があって地域包括支援センターへ行くことが難しければ、状況によっては、職員が訪問してくれる場合もあります。まずは、電話で相談してみましょう。
認知症について詳しく知りたい。教えてくれる?
はい、地域包括支援センターには認知症に詳しい専門職がいますので、気軽に相談してみましょう。認知症の特徴や、対応方法などを詳しく教えてくれるだけでなく、認知症の診断や治療に関する情報提供や、適切なアドバイスを受けることができます。
まとめ
この記事では、地域包括支援センターがどのような役割を持ち、どのような方が利用できるのか、具体的な相談内容の例などについて解説しました。
地域包括支援センターは、私たちの相談に応じて必要な支援・援助につなげてくれる機関です。将来、何かあったときに備えて、あらかじめ同センターと繋がっておくことを勧めます。
まずは、自分の住んでいる地域を担当するセンターに関する情報を収集することから始めてみましょう。