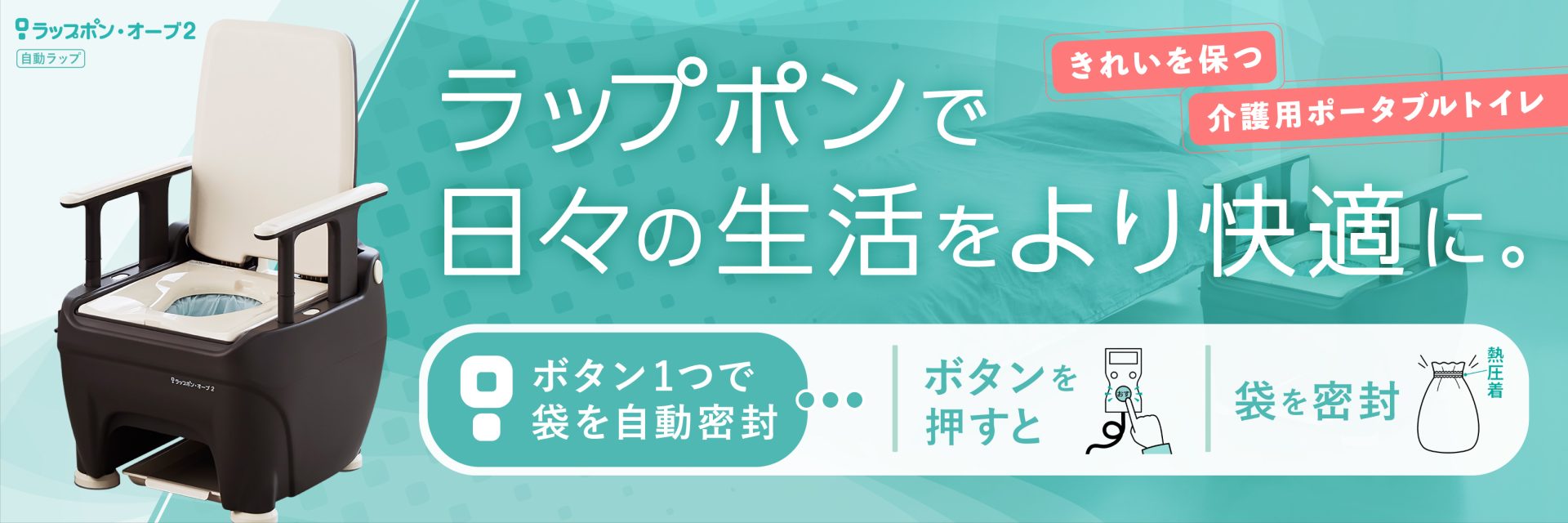「訪問入浴ってどんなサービス?」「入浴に介助が必要な状況とは、どのような場合?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
訪問入浴とは、自宅での入浴が難しい方を対象とし、介護スタッフが専用の移動式浴槽を持ち込んで、入浴を介助するサービスです。
この記事では、訪問入浴の料金、サービス内容、利用の流れを分かりやすく解説します。
Contents
訪問入浴とは
訪問入浴とは、訪問入浴サービスの事業者が利用者の自宅を訪問し、あらかじめ準備しておいた簡易浴槽を使って入浴の介護を行うサービスです。
このサービスは、看護師1名と介護職員2名(介護予防訪問入浴介護の場合は介護職員は1名となる)の計3名が訪問して介助を行うため、自宅での入浴が困難な高齢者でも安心して利用できます。
訪問介護との違い
訪問介護とは、高齢者の自宅にホームヘルパーが訪問し、身体介助(食事、入浴、排泄の介助など)や生活援助(調理、洗濯、掃除など)を行うサービスです。介護スタッフの1名体制でサービスが提供され、日常生活上のサポートや身の回りの世話のサービスが提供されます。訪問介護で入浴介助を受ける場合は、利用者の自宅にある浴槽で介助が行われます。
一方の訪問入浴は、自宅での入浴が難しい方を対象としており、簡易浴槽を持ち込んで入浴介助を行うなど、入浴に特化したサービスとなります。
利用の対象者・条件
訪問入浴の対象は、要介護認定で要介護1~5と判定され、自宅での入浴が困難で、主治医から入浴の許可が出ている方です(要支援1・2と判定された方は、介護予防訪問入浴を利用)。
このサービスで使用する簡易浴槽は、身体が横になったままで入ることができるため、次のような方たちにお勧めです。
- 寝たきりで自宅の浴槽では入浴が困難な方
- 身体に麻痺があり、シャワーチェアに安定的に座ることが難しい方
- 手足に障害があることで浴槽を跨ぐことができない方
- 身体機能の低下や関節の拘縮によって立位や座位が難しい方
- その他、自宅での入浴が困難な方 など
種類支給限度基準額
種類支給限度基準額とは、訪問入浴などの特定のサービスの利用限度額を市町村が独自に決められるルールを指します。一部の介護サービスの利用に限度額を設け、サービスの供給が特定の利用者に偏らないようにする仕組みです。
訪問入浴は、サービスを提供する事業所数が限られており、どの地域でも充分なサービス提供ができる体制が整えられている訳ではありません。よって、とある地域でサービスを提供する事業者が少ない場合、一人の利用者が頻繁にこのサービスを利用すると、他の利用者が利用できなくなるという不具合が発生してしまいます。
このような事態を防ぐため、種類支給限度基準額というルールが設けられ、訪問入浴などの一部のサービス利用に限度額を設け、特定の利用者による過度な利用を防止しているのです。
なお、お住まいの地域に種類支給限度基準額が設けられているかどうか気になる方は、担当のケアマネジャーに確認しましょう。
提供されるサービスと利用当日の流れ
訪問入浴は、次の流れでサービスが提供されます。利用当日の流れとともに説明します。
| 順序 | 内容 | 詳細 |
| 1 | 訪問入浴スタッフの訪問 | 予定時間に訪問入浴スタッフの訪問がある。 |
| 2 | 簡易浴槽の持ち込み・設置 | 自宅内に簡易浴槽が設置され、必要な物品が持ち込まれる。 |
| 3 | 体調の確認と、心拍数、血圧などのチェック | 利用者の体調が確認され、体温や血圧、脈拍などのバイタルチェックが行われる。 |
| 4 | お湯張り・入浴前準備 | 入浴車のボイラーから簡易浴槽に給湯される。入浴前の準備(タオルや利用者の衣類準備、更衣)が行われる。 |
| 5 | 入浴、皮膚の状態チェック | 簡易浴槽に入浴し、皮膚に異常が無いかチェック。頭や身体を洗う介助が行われる。 |
| 6 | 入浴を楽しむ | お湯に浸かって温まる。 |
| 7 | お湯から上がる | 上がり湯をしてベッドへ移乗する。 |
| 8 | 入浴後の体調確認と着衣 | 入浴後の体調確認が行われ、着衣や湿布を貼ったり、軟膏を塗ったりするなどの保湿ケアを行う。 |
| 9 | あと片付け | スタッフによって簡易浴槽の片付け、物品の片付けが行われる。 |
訪問入浴の所要時間
訪問入浴の所要時間は、約1時間です。内訳は次のとおりです。
- 簡易浴槽の準備、入浴前の準備:約15~20分
- 洗身介助:約10分
- お湯に浸かって温まる:約10分
- 着替え、後片付け:約15~20分
その他、医師の指示に基づく医療行為(例:保湿剤の塗布、爪切り、湿布の貼り替えなど)が行われる場合には、1時間を上回る場合があります。
準備する物品・設備
利用者側で準備する物品・設備は、次のとおりとなります。
| 項目 | 内容 |
| 物品 | 着替えバスタオル、タオルシャンプー、ボディソープ、入浴剤(利用者の好みやこだわりがある場合) |
| 設備場所 | 簡易浴槽を設置する場所(2畳程度)自宅のコンセント1~2ヶ所水道1ヶ所排水場所1ヶ所 など |
必要な物品・設備は、訪問入浴サービスを提供する事業所によって多少異なります。気になる方は、担当のケアマネジャーに確認しましょう。
訪問入浴の料金
訪問入浴の料金は、要介護度や介助の範囲によって異なります。次のとおりです。
| 要介護度 | 範囲 | 1回あたりの費用 |
| 要介護1~5 | 全身浴 | 1,266円 |
| 部分浴 | 1,139円 | |
| 清拭 | 1,139円 | |
| 要支援1・2 | 全身浴 | 856円 |
| 部分浴 | 770円 | |
| 清拭 | 770円 |
参考:「介護報酬の算定構造」 厚生労働省社保審-介護給付費分科会
※利用者の自己負担割合が1割の場合。
※※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制によって上記に加算が行われ、負担額が多少増える。
部分浴・清拭とは
部分浴とは、手浴や足浴などの身体の一部分だけ入浴し、介助するサービスで、清拭とは温かいタオルで身体の一部、または全部を拭くことを指します。
訪問入浴は全身浴を基本としますが、利用者のニーズや身体の状態によって、部分浴や清拭に切り替えることも可能です。
事情があって部分浴・清拭をしてほしいなどのご希望のある方は、担当のケアマネジャーや、訪問入浴を提供する事業所に相談すると良いでしょう。
訪問入浴のメリット
身体を清潔に保つことができる
訪問入浴を行うことにより、身体を清潔に保つとともに、かゆみや床ずれの予防をすることができます。また、寝具・衣類などの清潔保持にも繋がります。
生活の質を上げることができる
訪問入浴によって、生活の質を上げることが可能です。なぜなら、入浴によって血液循環、代謝機能を高めることができるだけでなく、多幸感やリラックス効果を得ることができるからです。
入浴は私たちにとって欠かすことのできない生活の営みの一つです。適切な訪問入浴サービスの利用は、生活の質を上げることに繋がります。
自宅での生活を継続できる
訪問入浴の適切な利用によって、自宅での生活を継続することができます。このサービスを利用できなければ、場合によっては施設へ入居せざるを得ない状態となり得るため、自宅での生活を希望する方にとっては不可欠なサービスだと言えます。
家族の負担軽減となる
適切に訪問入浴サービスを利用することによって、家族の負担を軽減することができます。自宅の浴槽を使って入浴する場合、家族が介助しようとすると、身体的に大きな負担を伴います。
また、家族の多くは入浴介助に慣れておらず、利用者を転倒させてしまったり、家族自身が腰を痛めてしまったりと、介護する側・される側のいずれも事故に遭う恐れがあります。
訪問入浴のデメリット
羞恥心を伴う
訪問入浴は、自分の入浴場面を見られてしまうことで、羞恥心(恥ずかしいと感じること)を伴います。訪問介護のスタッフとは言っても他人であるため、サービスの利用が結果としてストレスになることがあります。
訪問介護と比べると料金が高い
訪問入浴は、サービスを提供するスタッフが最低でも3名(看護師1名、介護職員2名)が必要となるため、その分、費用が高くなります。
訪問介護との比較は、下表のとおりです。
| 訪問入浴介護 | 訪問介護 | |
| 内容 | 利用者の入浴介助 | 利用者の身体介護、生活援助 |
| 料金 | 1,266円(全身浴) | 387円(身体介護で30分以上1時間未満の利用) |
よくあるトラブル
訪問入浴に関して、よくあるトラブルを紹介し、その対処法を示します。
| 例 | 項目 | 内容 |
| 浴槽の設置で部屋が狭くなる | トラブル内容 | 簡易浴槽を持ち込むため、約二畳分のスペースが必要になり、その分部屋が狭くなる。 |
| 対策法 | 事業所と契約する前に、実際に自宅を確認してもらい、家具の移動や物品の片付けが必要か双方でチェックして改善案を検討する。 | |
| サービス内容や時間に関する認識違い | トラブル内容 | 事前に想定していたサービス内容や時間と、実際の提供が異なり、サービス品質に満足できない。 |
| 対策法 | ケアプランを作成する時や、事業所と契約する際にサービス内容や時間について具体的に確認し、書面で残す。 |
訪問入浴を利用開始するまでの流れ
訪問入浴を利用するまでの流れは、次のとおりです。
| 順 | 内容 | 詳細 |
| 1 | 要介護認定の申請・判定 | 市町村の窓口に要介護認定の申請を行い、訪問調査を受けて要支援1・2、または要介護1~5のいずれかに判定される。 |
| 2 | ケアプランの作成 | 要介護1~5と判定された場合居宅介護支援事業所の介護支援専門員がケアプランを作成する。 要支援1・2と判定された場合地域包括支援センターの介護支援専門員、保健師などがケアプランを作成する。 |
| 3 | 訪問入浴サービス事業者との契約 | 訪問入浴サービスを提供する事業所を選び、契約を結ぶ。 |
| 4 | サービス利用開始 | ケアプランに基づいてサービスの利用を開始する。 |
| 5 | サービスの頻度、内容を調整する | 訪問入浴サービスの利用状況を見て、利用する頻度や内容を変更・調整する。 |
訪問入浴事業所の選び方
適切な訪問入浴の事業者を選ぶため、次のポイントを確認するようにしましょう。
看護・介護の有資格者がいる
訪問入浴は、看護師1名と介護職員2名の計3名体制でサービスが提供されます。これらサービスに従事するスタッフが、看護や介護に関わる専門資格を持っているかどうか確認しましょう。
| スタッフ | 資格の例 |
| 看護スタッフ | 看護師准看護師 |
| 介護スタッフ | 介護福祉士介護実務者研修介護職員初任者研修など |
資格の保有は、提供されているサービスの質を担保する一つの材料です。気になる方は事業所の担当者、またはケアマネジャーに確認すると良いでしょう。
評判の良い事業所を選ぶ
訪問入浴サービスに関して評価の高い事業所を選ぶため、担当のケアマネジャーから情報を収集しましょう。
サービス内容が丁寧であること、事故防止のための研修を行っているなど、事業所が行っている創意工夫が評判を呼び、その情報がケアマネジャーの耳に届いているはずです。
まとめ
この記事では、訪問入浴の料金やサービス内容、利用方法について解説してきました。
訪問入浴は、自宅の浴槽で入浴することが難しい方にとっては、とても便利なサービスです。適切に利用することで、住み慣れた自宅で自分らしい生活が続けられるようにしましょう。
参考文献
- 「訪問入浴介護」社会保障審議会介護給付費分科会(第220回)厚生労働省老健局
- 「どんなサービスがあるの? – 訪問入浴介護」介護事業所・生活関連情報検索 厚生労働省
- 「介護報酬の算定構造」 厚生労働省社保審-介護給付費分科会