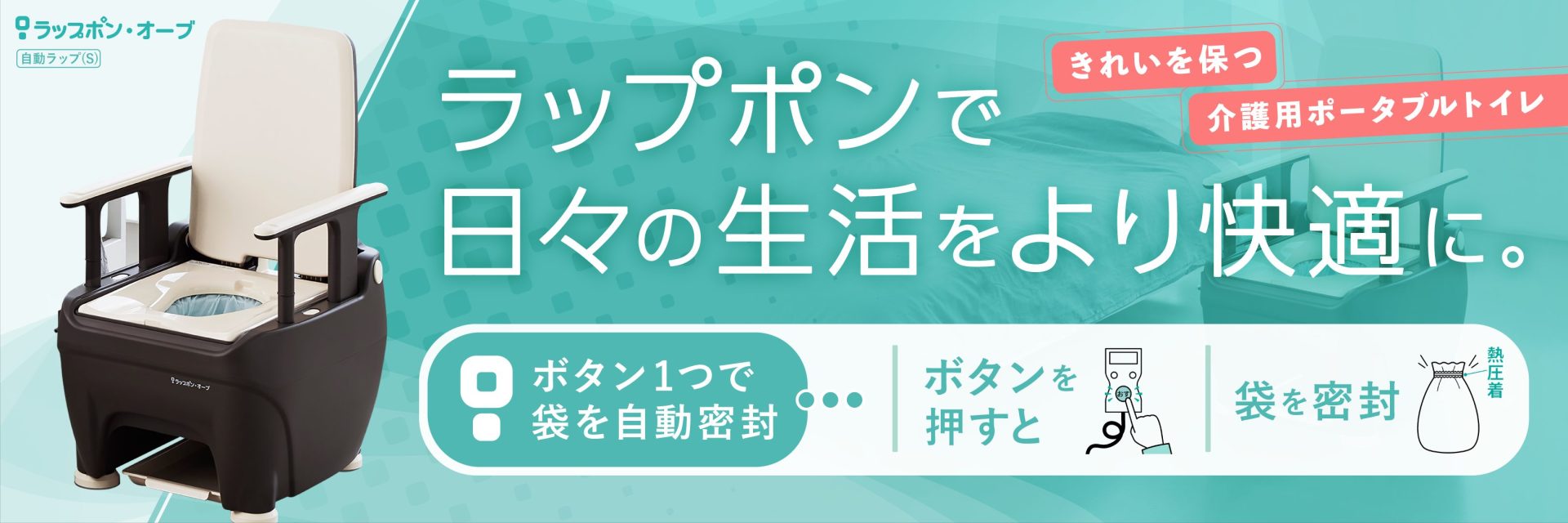通院や外出は、在宅介護を続けるうえで大きな課題の一つですが、介護タクシーを上手に活用すれば、車椅子や寝たきりの方でも、安全で快適に外出することができます。
この記事では、介護タクシーのサービス内容、料金、予約方法を説明するとともに、福祉タクシーとの違いを解説します。
Contents
介護タクシーとは
介護タクシーとは、主に介護を必要とする高齢者が自力で移動することが難しい場合に利用できる移動・送迎のサービスを指します。しかし、介護タクシーについては、行政による明確な定義や規定が曖昧で、各自治体や事業者等によって名称や運用が異なるのが現状です。
この記事では「介護タクシー」を、介護保険制度が適用される訪問介護サービスにおける「通院等のための乗車または降車の介助」と定義づけて説明します。
総務省では、「通院等のための乗車又は降車の介助」(いわゆる介護タクシー)を次のとおり規定しています。
| 居宅要介護者について、通院等のため、指定訪問介護事業者の訪問介護員等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助 |
出典:「訪問介護における通院等乗降介助(いわゆる「介護タクシー」」総務省
つまり、介護タクシーとは、介護保険制度における訪問介護サービス内の一つの形態であり、主に利用者がかかりつけの医療機関に通院する目的で利用する移送・送迎のサービスです。
このほか、日常生活上でしなければならない外出の用事(選挙における投票や、預貯金の引き出し、送金など)を済ませる際に利用することができます。
介護タクシーのサービス内容
介護タクシーでは、自動車による移動に加えて、次のような介助サービスを受けることができます。
- 車両に乗車する前と後とで必要となる移動の準備
- 移動車両への乗車・降車に伴う動作の介助
- 車両を降りてから目的地(投票所の受付や病院の受付、銀行の窓口など)への移動の介助
- 病院の受付などでの診療に関する手続きの支援
福祉タクシーとは
介護タクシーに似たサービスとして、福祉タクシーがあります。
福祉タクシーとは、自力での移動に制限のある人が利用する移動支援のサービスを指します。
国土交通省は「福祉タクシー」を次のように紹介しています。
| 福祉タクシーとは、道路運送法第3条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送のことをいう。 |
福祉タクシーは移動に制限のある方を対象にしており、介護タクシーのように介護保険制度の利用者だけを対象にしている訳ではありません。
自治体によってルールが異なりますが、多くの市町村が、地域に住む高齢者や障害者に移動の機会を持ってもらえるよう、福祉タクシー制度(費用助成)を実施しています。
以下、自治体が行っている福祉タクシー事業、または利用助成制度の例を紹介します。
東京都北区の福祉タクシー券
東京都北区は、歩行が難しく、自宅で生活する心身障害者の外出を支援するため、福祉タクシー券を支給しています。
福祉タクシー券とは、該当する方が外出する際に利用できるタクシーチケットのようなもので、一ヶ月あたり500円券が7枚、100円券5枚が支給されます。同区と契約した会社のタクシーを利用するときに利用することができます。
千葉県野田市の福祉タクシー
千葉県野田市は「福祉タクシーサービス事業」を実施しており、主に介護が必要な高齢者が通院のために同市と契約した
タクシー会社の福祉タクシーを利用した場合、運賃の半額を助成(助成上限額は1枚につき1,000円)するというものです。
介護タクシーと福祉タクシーの違い
ここでは、これまで述べてきた介護タクシーと福祉タクシーの違いを下表にて説明します。
| 介護タクシー | 福祉タクシー (東京都北区の場合) | |
| 本記事における定義 | 介護保険の訪問介護における通院等乗車または降車の介助等 | 自力での移動に制限のある人が利用する移動・送迎のサービス |
| 目的 | 通院など日常生活を送るうえで欠かせない外出の支援のため | 自宅で生活する障害者の外出の支援のため |
| 対象 | 要介護認定を受け、要介護状態と判定を受けた者で、自宅に住み、公共交通機関などでの移動が困難な方 | 身体障害者手帳の等級が次のいずれかに該当する方 下肢、体幹機能障害1~3級視覚障害1・2級内部機能障害1~3級 など |
| 利用シーン | 通院など日常生活を送るうえで必要な外出に限られる。 | 特に利用の目的に関して限定はされていない。 |
| サービス内容 | 車両に乗る前の準備、乗り降りの介助、病院の受付までの移動の介助、受診の手続きのサポートなど | 原則、目的地までの移動のみ |
| 事前申請等 | ケアプラン内に同サービスの利用計画を含め、サービス提供事業所との契約が必要 | 事前に役所への申請が必要 |
| 資格の有無 | 介護分野の資格を持つ者運転・介助を行う。 | 事業者・乗務員によって異なる。 |
| 費用 | 運賃は事業者によって異なるが、介助にかかる費用は介護保険が適用される(詳しくは後述)。 | 福祉タクシー券として、一ヶ月あたり500円券が7枚、100円券5枚が支給されるが、その差額分が自己負担となる。 |
上記のとおり、介護タクシーは介護保険制度の適用を受けるため、利用の目的や対象者が限定的で、介助費用については
1割の自己負担(原則)で済みます。
一方で、福祉タクシーについては、運賃の一部助成を受けられるという点に特徴がありますが、各自治体の定めるルールに基づいて運営されるため、目的や対象者が一律ではありません。
介護タクシーの利用料金
介護タクシーを利用した場合、移動(移送)料金+介助費用+介護器具のレンタル代がかかります。
以下、一つずつ説明します。
移動(移送)料金
移動(移送)料金とは、介護タクシーを利用して目的地へ移動したことに伴ってかかる運賃を指します。
運賃は、一般的なタクシーを利用する場合と同じで、利用した地域や移動した距離、かかった時間によって変動します。
不安のある方は、事前にケアマネジャーに相談すると良いでしょう。
介助費用
介助費用とは、介護タクシーの利用に伴って発生する外出準備や、車両の乗り降りの介助にかかる費用です。
これらの介助サービスは介護保険が適用されるため、利用者は費用の1割を自己負担するだけで済みます。
1回あたりの自己負担額は100円程度です。
ただし、所得によっては負担割合が異なるため、200円〜300円になる場合もあります。
また、往復で介助サービスを利用する場合は、行きと帰りの両方で費用がかかります。
なお、介助時間が20〜30分を超える場合や、乗降介助以外の身体介護(例:食事やトイレの介助など)が必要な場合は
「通院等のための乗車または降車の介助」ではなく「身体介護」として扱われます。この場合、料金が高くなりますのでご注意ください。
福祉用具等のレンタル料
福祉用具等のレンタル料とは、介護タクシー事業者が準備した福祉用具や医療機器の利用に伴ってかかる費用です。
これは、利用者が介護タクシーに備え付けられている車椅子や、ストレッチャー(利用者が寝た状態で移動することができる器具)、酸素ボンベなどの医療機器などを利用した場合にかかるレンタル代です。
費用の例は次のとおりです。
| 器具 | レンタル費用の例 |
| 車椅子 | 約500円〜2,000円 |
| ストレッチャー | 約1,000円〜6,000円 |
| 酸素ボンベなどの医療機器 | 約3000円~ ※器具によって異なる |
なお、自身の車椅子などを使用する場合は、これらの費用はかかりません(介助費用は別)。
料金に不安がある方は、ケアマネジャーに相談しましょう。
介護タクシーの利用方法
介護タクシーの利用条件
前述のとおり、介護タクシーを利用できるのは、要介護認定において要介護1~5と判定された方で、かつ自宅に住み、公共交通機関を利用した移動が難しい方です。
また利用目的については、医療機関への通院など、日常生活を送るうえで欠かせない用事での利用に限られます。
介護タクシーの利用の流れ
ケアマネジャーに相談・ケアプランの作成
介護タクシーの利用を希望する場合は、まず担当のケアマネジャーにその旨を相談しましょう。
ケアマネジャーは、利用者がどのような場面で困っているかなどを聞き取ります。そのような要望のなかで介護タクシーが必要と判断されれば、介護保険が適用されるようにケアプランに組み込んでもらえます。
事業者の選定・契約
次に介護タクシーのサービス提供事業所を選択します。予約の方法や費用負担など、様々な情報を収集して選ぶのが理想的ですが、どの介護タクシー事業者が良いか分からない方も少なくないでしょう。そのような方は無理して判断せずに、担当のケアマネジャーが紹介してくれた業者を選ぶと良いでしょう。事業者との契約は、ケアマネジャーがサポートしてくれるので安心です。
介護タクシーを利用する
実際に介護タクシーを利用する日時が決まったら、事業者へ電話連絡して予約を取りましょう。予約する日時、目的と目的地、利用する介護器具の有無、その他の注意点を伝えると良いです。
介護タクシーを利用する際の注意点
ここからは、介護タクシーを利用するうえでの注意点を説明します。
家族は同乗できない
原則として、介護保険が適用される介護タクシーは、利用者本人だけが乗車でき、家族は同乗することができません。
これは、介護保険サービスを利用できるのが要介護認定を受けた利用者本人に限られているためです。
ただし、本人が認知症に罹患しており、家族の付き添いがないと不安になるなど、市町村が特別な事情があると認めた場合は、特例として同乗が認められることがあります。
家族の同乗が必要な場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
タクシー移動だけの依頼はできない
介護タクシーはタクシー移動だけの依頼はできません。なぜなら、介護タクシーは、単なる移動手段ではなく、身体介護を伴う訪問介護サービスの一環として提供され、介護保険制度が適用されるためです。
サービス内容には、車両での移動に加え、外出の準備や乗り降りが含まれます。
単に移動手段として利用する場合、通常のタクシー会社を利用してください。この場合、当然のことながら介護保険は適用されず、運賃は全額自己負担となります。
介護タクシーの選び方
料金設定の確認
料金設定を確認しましょう。先述のとおり、介護タクシーの運賃は移動した距離、移動にかかった時間によって変動します。
また、運賃の計算方法は介護タクシー事業者によって異なるため、あらかじめ見積もりを取ることを勧めます。
見積もりは介護タクシー事業者へ直接依頼することも可能ですが、担当のケアマネジャーを経由して依頼すると良いでしょう。
有資格者がいるか
介護タクシー事業者の介護スタッフ・乗務員は、介護職員初任者研修修了などの有資格者です。それでも十分ですが、介護分野の上位資格である実務者研修修了者や介護福祉士などの保有者がいれば、サービス品質が一定以上であると期待できます。
評判
お試しで介護タクシーを利用し、窓口スタッフや乗務員の対応が十分に満足できるかどうか確認することを勧めます。
もし万が一、対応品質に問題があれば、遠慮せずに担当のケアマネジャーに伝えましょう。乗務員を変更してくれたり、事業者自体を変更してくれるなどの対応が期待できます。
まとめ
この記事では、介護保険制度が適用される「介護タクシー」を中心に、そのサービス内容や利用方法、そして「福祉タクシー」との違いについて解説しました。
介護タクシーは、単なる移動手段ではありません。車両の乗り降りや、病院での手続きなど、外出に必要な介助も合わせて提供されるサービスです。
そのうえで介護保険が適用されるため、費用を抑えて利用できるメリットがあります。
在宅介護において、通院や外出は大きな課題ですが、介護タクシーを上手に活用することで、その負担は大きく軽減されます。本人やご家族だけで悩まず、まずは担当のケアマネジャーに相談し、適切なサービスを利用して、安全で快適な移動を実現しましょう。