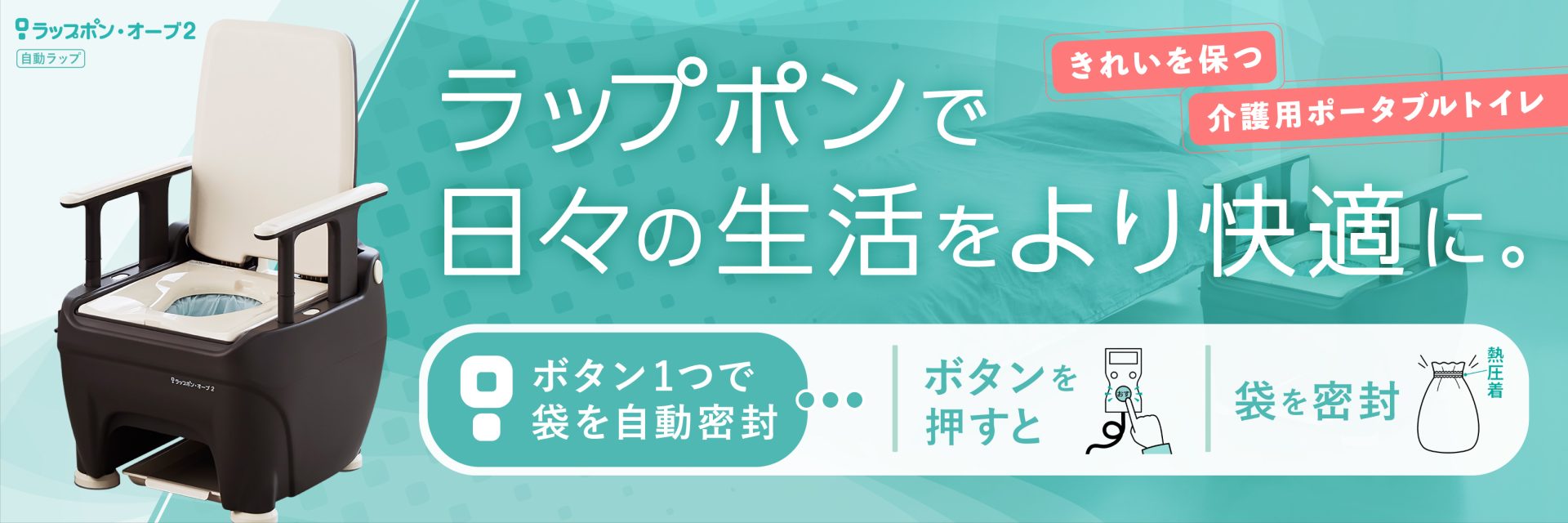通所リハビリテーション(デイケア)は、利用者がセンターに通ってリハビリテーションや介護を受けられる介護保険サービスの一つです。
しかし、具体的にどのようなサービスが受けられるのか、デイサービスとの違いは何かなど、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、通所リハビリテーションの概要を説明するとともに、その特徴や費用、サービス内容などを分かりやすく解説します。
デイケア(通所リハビリテーション)は、利用者がセンターに通ってリハビリテーションや介護を受けられる介護保険サービスの一つです。
しかし、具体的にどのようなサービスが受けられるのか、デイサービスとの違いは何かなど、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、デイケアの概要を説明するとともに、その特徴や費用、サービス内容などを分かりやすく解説します。
Contents
デイケア(通所リハビリテーション)とは
デイケア(通所リハビリテーション)を簡単に説明すると、「介護やリハビリテーションが必要な高齢者がセンターに通って利用するサービス」です。
このサービス事業所は、病院や診療所、介護老人保健施設に併設されることが一般的で、リハビリテーションだけでなく、医療的なケアも提供している点に特徴があります。
デイケア(通所リハビリテーション)の利用目的
デイケアの主な利用目的は、専門家の指示のもとで専門的なリハビリテーションを受け、心身機能の維持・向上を図ることです。具体的には、歩行能力の改善、日常生活動作の訓練、言語機能や嚥下機能(食べ物や飲み物を口から胃へ送り込む一連の動作)の回復などに取り組みます。
また、利用者が他の参加者と交流することで社会的孤立を防ぎ、生活の質を高める効果も期待できます。さらに、定期的に施設を利用することで、家族の介護負担を軽減し、在宅介護を継続しやすくする役割も担っています。
デイサービス(通所介護)との違い
デイケアに似たサービスに、通所介護(デイサービス)があります。両者はどのように違うのでしょうか。以下のとおりです。
| デイケア(通所リハビリテーション) | デイサービス (通所介護) | |
| 目的 | リハビリテーション、心身機能の維持や回復、一部の介護など | 日常生活上の介護、レクリエーション、日常生活の活性化 |
| 対象 | 要支援1・2:介護予防通所リハビリテーション(後述)要介護1~5:通所リハビリテーション | 要介護1~5 |
| 主なサービス | 食事の提供身体介助、日常生活上の世話リハビリテーション 医療的ケア ほか | 食事の提供身体介助、日常生活上の世話レクリエーション 機能訓練 ほか |
| 費用 | 利用回数や要介護度によって異なる。 | 同左 |
| 特徴 | リハビリを通して心身機能の維持、向上を図ることができる。 | レクリエーションを通して充実した余暇を送ることができ、他者と交流を図ることができる。 |
このように、どちらも事業所に通って一日を通して介護サービスを受けられることに変わりはありませんが、最大の違いは専門的なリハビリテーションが受けられるかどうかです。
介護予防通所リハビリテーションとは
介護予防通所リハビリテーションは、通所リハビリテーションの一種です。要介護認定で要支援1・2の認定を受けている方が対象で、要介護状態にならないよう「予防のため」にリハビリテーションを受けるサービスのことを言います。
要介護1~5を対象としている通所リハビリテーションとの違いは次の通りです。
| 要介護1~5を対象とした通所リハビリテーション | 介護予防通所リハビリテーション | |
| 目的 | 心身機能の維持・回復 | 要支援状態の維持、要介護状態にならないための予防 |
| 対象 | 要介護1~5 | 要支援1・2 |
| 主なサービス内容 | 主に心身機能の回復のためのリハビリテーション日常生活上の動作に関する訓練身体介護 など | 心身機能の維持・向上のリハビリテーション口腔機能の向上栄養改善 など |
デイケアの一日の流れ
デイケアの一日の流れは次のとおりです。
| 時間 | 項目 | 内容 |
| 8:30~ | 送迎 | 送迎車で事業所まで送迎してくれる。 |
| 9:00~ | 体調確認 | 事業所に到着し、看護師が利用者の血圧、脈拍、体温を測定し、体調に問題がないか確認する。 |
| 10:00~ | ラジオ体操、または個別体操・リハビリ | 集団で体操をする。体操が難しければ、個別の体操・リハビリテーションを行うことがある。 |
| 10:30~ | 入浴 | 心身状況によっては入浴介助が受けられる。 |
| 11:00~ | レクリエーション | 簡単に体を動かす体操や、計算ドリルを使った脳トレがある。 |
| 11:30~ | 口腔体操 | 昼食の前に、嚥下機能(食事の飲み込み)が良くなるように口の動きを活発化させる口腔体操を行う。 |
| 12:00~ | 昼食 | 口腔状態に合わせた食事が提供され、利用者によっては食事介助が行われる。 |
| 13:00~ | 集団体操、または個別リハビリ | 理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーション。集団での体操や、個別のリハビリテーションが行われる。 |
| 14:00~ | レクリエーション | 午後のレクリエーションでは、習字、折り紙、盆栽などの趣味の活動が行われることがある。 |
| 15:00~ | おやつ | 利用者にお茶・おやつが提供される。 |
| 16:00~ | 自宅まで送迎 | 自宅までの送迎をしてくれる。 |
上記は一般的なデイケアの一日の流れです。事業所によって時間や内容が異なりますので、気になる方は担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に確認してください。
デイケアの利用の対象者・条件
デイケアを利用できるのは、要介護認定で要介護1~5と判定された方で、かつリハビリテーションや医療的ケアを必要としている方です。
デイケアを利用するためには、主治医が作成した診断書が必要になります。
もし主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師やデイケア施設に在籍する医師などの診断でも問題ありません。
主に次のような方たちが利用しています。
- 高齢になって心身機能が低下しており、その維持・回復を目指したい方
- 脳梗塞を患い、右半身が麻痺するなどの障害を負い、自立した日常生活を送るためのリハビリテーションを必要とする方
- 嚥下機能(食べ物を飲み込む力)が低下し、この機能の回復のためにリハビリテーションを必要とする方 など
デイケアにはリハビリの専門家が配置されている
デイケアの最大の特徴は、医療資格を持つリハビリテーションの専門職が配置されていることです。これにより、利用者一人ひとりの身体状況や目標に応じた専門的なリハビリプログラムを受けることができます。
リハビリの専門職には下記の3つがあります。
| 専門職 | 特徴 |
| 理学療法士 | 立つ・歩く・座るといった基本的な動作能力の回復を専門とします。 |
| 作業療法士 | 食事・入浴・着替えなどの日常生活動作や社会適応能力の向上を支援します。 |
| 言語聴覚士 | 話す・聞く・食べるといった言語や聴力、嚥下機能の回復を専門とします。 |
また、上記のようなリハビリの専門家以外に、医師や看護職員も配置されています。
デイケアで提供されるサービス
デイケアで提供されるサービスは次のとおりです。
リハビリテーション
デイケアには、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテーション分野のセラピストが勤務しており、利用者の心身機能の維持・回復のためのリハビリテーションが提供されます。利用者は自身の目的や希望に合わせて、集団、または個別のリハビリテーションを行います。
集団と個別それぞれのリハビリテーションの特徴は以下のとおりです。
| リハビリの種類 | 特徴 |
| 集団 | 複数の利用者が一緒に行う体操やレクリエーション活動。他の参加者と交流しながら楽しく体を動かすことで、運動習慣の継続やモチベーション維持につながる。 |
| 個別 | 専門職と一対一で行うリハビリです。利用者の身体状況や目標に合わせた細やかなプログラムが組まれ、より集中的な訓練を受けられる。 |
食事の提供
デイケアでは、利用者の口腔機能に合わせた食事が提供されます。ただし、利用者の利用時間が1〜4時間の場合は、食事は提供されません。
介護サービス
利用者の心身状況に応じて、食事、入浴、排泄などの身体介助が提供されます。利用者が自立している部分は自身で行ってもらうという「自立支援」を原則としたサービス提供となります。
健康管理・医療的ケア
デイケアには看護師が配置されているため、入居者の脈拍、血圧、体温を測り、健康管理を行ってくれるだけでなく、褥瘡(床ずれ)の処置、湿布の貼り替えなどの医療的なケアをしてくれます。
レクリエーション(余暇活動)
デイケアでは、利用者の生活意欲を高めるためのレクリエーション・余暇活動が提供されます。具体的には、健康体操、脳トレなどが行われたり、季節に応じたレクリエーションが実施されます。
デイケアの費用
デイケアの費用は、事業所の規模や所要時間によって費用が設定されてます。
費用目安は下記の表のとおりです。
| 要介護度 | 1ヵ月あたりの費用※自己負担割合が1割の場合 |
| 要支援1 | 2,268円 |
| 要支援2 | 4,228円 |
| 要介護度 | 1回あたりの費用※自己負担割合が1割の場合※6時間以上7時間未満の場合 |
| 要介護1 | 715円 |
| 要介護2 | 850円 |
| 要介護3 | 981円 |
| 要介護4 | 1,137円 |
| 要介護5 | 1,290円 |
出典:どんなサービスがあるの? – デイケア(通所リハビリテーション)介護事業所:生活関連情報検索 厚生労働省
なお、上記には、利用者の食事代やおむつ代などの日常生活費、レクリエーション材料費などは含まれていません。また、入浴介助や口腔機能向上指導など、個別でサービスを受ける場合は別途、追加料金がかかります。
デイケアのメリット
デイケアでは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職によるリハビリテーションが提供されますので、現在の心身機能を維持したい、回復させたいというニーズに適うサービスです。
行われるリハビリテーションに効果があれば、健康寿命を伸ばしたり、認知症の予防につながったりするメリットがあります。
また、事業所が病院などの医療機関に併設されているため、安心してサービスを利用できる点もメリットだといえるでしょう。
デイケアのデメリット
送迎に関する不便さ
一般的なデイケアは、事業所の準備した送迎車を使って利用者の家まで迎えに行き、サービスが終わって家まで送り届けてくれます。
一見すると便利なように見えますが、利用する側としては、送迎車の時間に合わせて準備をする必要があります。また、時間に遅れないように気を遣ったり、他の利用者さんの都合で送迎時間が多少前後したりすることもあるため、不便な点があることも理解しておきましょう。
他の利用者との人間関係
デイケアは様々な高齢者が利用しています。他の利用者との適度な交流のなかで、趣味が共通する人たちなどとの交遊が拡がる一方で、気が合わない人との人間関係でストレスを感じることもあるでしょう。
集団リハビリテーションに関する不満
デイケアでは、個別と集団のリハビリテーションが実施されますが、集団リハビリテーションが中心となる事業所では、自分のペースや目標にあったリハビリテーションができずに不満が募ることもあります。内容によっては「幼稚すぎる」「面白くない」など、自分のニーズに合わないことがあります。
デイケアを利用するまでの手順
デイケアを利用するまでの流れは次のとおりです。
1:要介護認定を受ける
2:ケアマネージャーに相談
3:利用したい施設の見学
4:医師に診断書の作成を依頼
5:施設側と面談
6:契約・利用(通所)開始
上記はあくまでも一般的な例です。施設によって詳細が異なりますので、注意してください。
デイケアを選ぶ際のポイント
デイケアを選ぶ際のポイントを紹介します。
目的や希望に合うリハビリテーションの内容か
デイケアに通う目的と、希望するリハビリテーションの内容を提供してくれる事業所か確認しましょう。事前に体験利用をしたり、見学をしたりして、目的や希望に適うリハビリテーションの内容かどうか、確認しましょう。
専門職と職種間の連携体制が整っているか
リハビリテーション分野の専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが配置されている事業所か確認しましょう。
また、定期的なカンファレンスが行われ、医師や看護師などとの情報共有や連携がスムーズに行われているかチェックすると良いでしょう。
設備が整っているか
事業所に医療、リハビリテーション、介護などの設備が整っているか確認しましょう。具体的には次のような設備があると良いでしょう。
- 筋力トレーニングのマシン、歩行訓練台、歩行階段、スロープなどの運動療法器具
- ペグ、アクリルコーン、おはじき、ビー玉、食器・お箸の自助具などの作業療法に関する物品 ほか
事業所の雰囲気と利用者の様子
実際に事業所を訪問して見学し、明るさや清潔さを確認し、自分が通所して快適に、リハビリテーションができるかどうか判断しましょう。
また、利用者同士のコミュニケーションや、スタッフとのやり取りが和やかな雰囲気が行われているかどうかチェックし、自分の好む雰囲気かどうかを知ると良いでしょう。
まとめ
この記事では、デイケアの概要を説明するとともに、提供されるサービス内容やメリット・デメリットを紹介しました。
興味のある方は、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに相談することから始めましょう。
参考文献