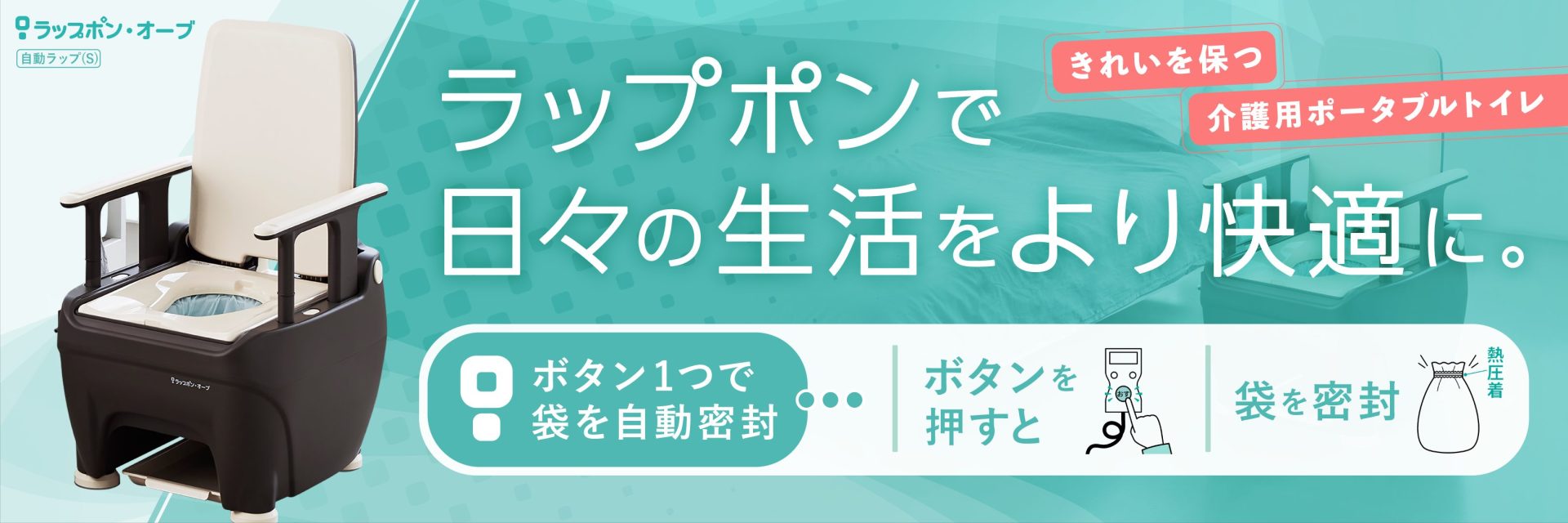家族の介護が始まり、漠然と不安を感じている方もおられるでしょう。
介護が必要な状態になっても、住み慣れた家で暮らし続けるために知っておきたいのが、地域包括ケアシステムです。
この記事では、地域包括ケアシステムとは何か、具体的な事例を通してその仕組みを分かりやすく解説します。
Contents
地域包括ケアシステムとは
地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、その能力に応じて自立した日常生活を送ることができるよう、
住まい、医療、介護、介護予防、そして生活支援が一体的に提供される体制のことです。
おおむね30分で駆けつけられる圏域(日常生活圏域)を単位として、認知症の方や一人暮らしの高齢者、また医療的ケアが必要な方々を含め、誰もが質の高いケアや必要なサービスを途切れることなく受けられるよう、地域の実情に合わせた体制の整備が求められています。
地域包括ケアシステムの対象者
地域包括ケアシステムの対象は、主に地域に住む65歳以上の高齢者やその家族です。
要介護認定の有無は問われず、地域に住む高齢者であれば全員がその対象となります。
しかし、自治体・地域によっては、高齢者だけでなく、難病患者、重度の知的・身体の障害を有する者・児、精神障害者など、地域生活を営むうえで支援を必要とする全ての人を対象とする動きもあります。
地域包括ケアシステムが求められる背景
ここでは、地域包括ケアシステムが求められるようになった背景を説明します。
高齢化の進展
我が国では、高齢化の進展に伴って、特に75歳以上の高齢者(後期高齢者)の増加が顕著です。
後期高齢者は要介護認定率や認知症の発生率が高く、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ方たちが少なくありません。
これに加えて、一人暮らしの高齢者や高齢夫婦のみの世帯も増加しており、家族だけでの介護では対応が難しくなって
います。
このような背景から、高齢者が自宅での生活を継続できるよう地域包括ケアシステムのような体制づくりが求められるようになりました。
介護保険サービス利用者の急増
2000年に始まった介護保険制度では、高齢者介護を社会全体で支えるという理念のもと、介護を必要とする方へ公的な
介護サービスが届けられるよう制度化されました。
しかし、年々その利用者が増加しているため、公的サービスの提供だけでは賄いきれず、これに合わせて、民間企業や
ボランティアなどが有機的に連携し合い、要介護高齢者を支える地域づくりが求められるようになりました。
ニーズの多様化
社会構造の変化によって私たちの生活スタイルが変わり、高齢者や家族の抱えるニーズが多様化しています。
例
・身寄りのない一人暮らしで、認知症を発症して支えてくれる人がいない。
・医療や介護資源の乏しい山間部で、高齢者夫婦が二人で暮らしている。このまま自宅での生活を継続したい。
・医療的なケアが必要だが、自宅での生活を希望する後期高齢者 など
それぞれが様々な課題を抱えていながらも、住み慣れた地域で一人ひとりが自分らしい暮らしを続けるためには、
公的なサービスだけでは限界があります。
よって、これらのニーズを満たしていくためには、上記に加えて、私的団体や民間による生活支援が一体的に提供される体制の構築が求められるようになったのです。
地域包括ケアシステムが目指すもの
地域包括ケアシステムの目指す姿、目標はどのような点にあるのでしょうか。以下、解説します。
| 項目 | 内容 |
| 高齢者の尊厳と自立を支える | 高齢者が疾患や障害を抱えていても、自分らしさを保ち、自立した生活を送ることができるよう支援すること |
| 住み慣れた地域における暮らしの継続 | 高齢者が住み慣れた地域で人生の最期を迎えるまで、医療、介護などのサービスを受けながら自分らしい生活を継続すること |
機関地域包括ケアシステムを構成する5つの要素
地域包括ケアシステムの実現のためには、次の5つの要素が有機的に連携し、切れ目なく包み込むように、総合的なケアが提供されることが重要です。
住まい
自宅、または入居する施設を指します。生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と経済力に適った住まいが確保されていることが、地域包括ケアシステムの前提となります。高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた住環境が必要とされます。
医療
病院、クリニックなどの医療機関を指します。日常の医療と、緊急時の医療体制が整い、相互に連携し合って、通院・入院の医療体制が整っている状態です。また、必要に応じて、往診などの訪問医療が提供されます。
介護
要介護認定において要介護1~5と判定された高齢者に対して、提供される介護サービスを指します。
介護サービスには次の種類があります。
- 居宅サービス:訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーションなど
- 通所サービス:デイサービス、デイケアなど
- 施設サービス:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など
- 地域密着型サービス:グループホーム、小規模多機能型居宅介護など
- その他のサービス:住宅改修、福祉用具貸与、特定福祉用具販売など
介護予防
要介護認定において要支援1・2と判定された高齢者が、要介護状態にならないための介護予防サービスや、重度化を防ぐための様々な取り組みを指します。介護予防サービスには次の種類があります。
- 居宅サービス:介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーションなど
- 通所サービス:介護予防通所リハビリテーション
- 施設サービス:介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護など
- 地域密着型サービス:小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護など
- その他のサービス:介護予防福祉用具貸与など
生活支援・福祉サービス
地域における見守りや、買い物支援、配食サービスなどの生活支援を指します。自治体による公的なサービスとして
提供されるケースもあれば、民間企業や近隣住民、NPO法人、ボランティアなどによる支援があります。
これら5つの構成要素が連携できるよう日頃からネットワークを作っておいたり、効果的な医療・介護サービスが
要介護高齢者のもとへ届いているかどうか確認、管理したりするのが地域包括支援センターです(後述)。
地域包括ケアシステムを推進する機関
地域包括ケアシステムの実現に向けて、中心的な役割を担っているのが、地域包括支援センターです。
この機関は、地域の高齢者の介護・医療・福祉に関する相談に応じるとともに、高齢者の権利を守ったり、地域の支援体制づくりをサポートしています。
以下の記事では、地域包括支援センターの詳しい役割について説明しています。興味がある方はご覧ください。
『地域包括支援センターとは?役割や利用対象者、相談内容例を解説』
地域包括ケアシステムのメリット
地域包括ケアシステムは、高齢者や家族にとってどのようにメリットになるのでしょうか。それぞれ整理して説明します。
高齢者のメリット
地域包括ケアシステムの構築が進み、自宅で医療を受けられる体制が整えば、医療的なケアが必要な高齢者でも、自宅で生活することが可能になります。在宅医療を提供する事業所と、介護サービスを提供する事業所の連携のもと、質が保たれた医療・介護サービスを受けることが期待されます。
家族のメリット
地域包括ケアシステムが整えば、自宅などで介護をしている家族の身体的、精神的な負担が軽減されます。介護保険制度による公的サービスに合わせて、地域における民間やNPOなどの支援を受けながら、家族の孤立化を防ぐことが可能でしょう。
地域社会におけるメリット
地域包括ケアシステムが機能し、介護予防が効果的に進められれば、要介護状態の重度化を防ぐことができ、膨れ上がる介護保険財政を節減することができます。
また、地域の支え合い体制の構築が進めば、住民同士の社会的な交流が促進され、高齢者の生きがいの創出につながります。これらの互助関係によって地域に活力が生まれ、より住みやすい地域にすることが可能です。
地域包括ケアシステムの具体例
ここでは、地域包括ケアシステム構築へ向けた取り組みを進めている東京都世田谷区の事例を紹介します。
東京都世田谷区の事例
世田谷区は、人口規模が東京23区のなかでも最大規模で、都内有数の住宅地であるとともに、大規模な都市公園や
商業地、私立学校等があります。同区では、地域活動団体・NPO・事業者等との協働によるまちづくりを推進しており、
地域包括ケアシステムの構築に向けて下記の取り組みを進めています。
出典:「地域包括ケアシステム構築へ向けた取組事例~東京都世田谷区の取組~」厚生労働省
| 要素 | 内容 |
| 医療 | 〇世田谷区医療連携推進協議会による在宅医療推進の取り組み 〇ケアマネタイム(ケアマネジャーが医師に相談しやすいよう、あらかじめ設定された時間)や 医療と介護の連携シートによる福祉と医療の情報を共 |
| 介護 | 〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用・事業展開の推進 |
| 介護予防 | 〇社会参加を通じた介護予防による高齢者の居場所と出番の創出 〇中高年層ボランティアの活動促進(買い物支援等) |
| 住まい | 〇認知症高齢者グループホームや社会資源等を有効活用した都市型軽費老人ホーム等の整備 〇区立高齢者センターを民営化し、都市型軽費老人ホームを開設 |
| 生活支援 | 〇住民団体・社会福祉協議会主体の地域活動の推進 〇空き家や空き部屋を活用した地域活動(サロンや小規模のデイサービス等)の拠点を整備 |
地域包括ケアシステムに関する課題
ここからは、地域包括ケアシステムに関する課題を説明します。
人材不足
医療や介護に携わる人材が不足していることで、地域包括ケア体制そのものが整わないという問題です。特に介護人材に関しては、2040年度には272万人が必要とされていますが、約57万人が不足すると予測されています(厚生労働省)。
医療・介護人材の確保は、包括的支援体制の構築に向けた喫緊の課題だと言えるでしょう。
連携不足
医療機関や介護サービス提供事業所などの社会資源があっても、それが連携していなければ地域包括ケアシステムの効果は十分に発揮できません。先述のとおり、地域包括支援センターが中核的な役割を担いながら、専門機関・支援機関などをネットワークで繋ぎ、有機的に連携できるような準備・情報の共有が求められています。
財源確保の難しさと地域格差
地域包括ケアシステムの構築には、十分な財源が必要です。少子高齢化の進む我が国においては、介護保険料を払う現役世代が少なくなり、十分な財源の確保が難しい状況にあります。
加えて、各市町村の財政状況によって、地域包括ケアシステムへの取り組みに差が生じます。財政的にゆとりのある自治体は、包括的な支援事業を積極的に推進できる一方で、財政的に厳しいケースでは、国が定める最低限のサービス提供に留まることがあります。
限られた財源のなかで、地域の実情に合わせてどのようにケアシステムを構築していくことができるのか、大きな課題だと言えるでしょう。
まとめ
この記事では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための仕組み、地域包括ケアシステムについて解説しました。
少子高齢化・核家族化が進み、家族だけで高齢者の生活を支え続けることは非常に困難です。
しかし、地域における支え合いのネットワーク=地域包括ケアシステムを理解し、活用することで、高齢者だけでなく家族も安心して暮らすことが可能になります。
お住まいの地域において、地域包括ケアシステムが構築されているかどうか知りたい方は、地域包括支援センターへ相談してみてください。