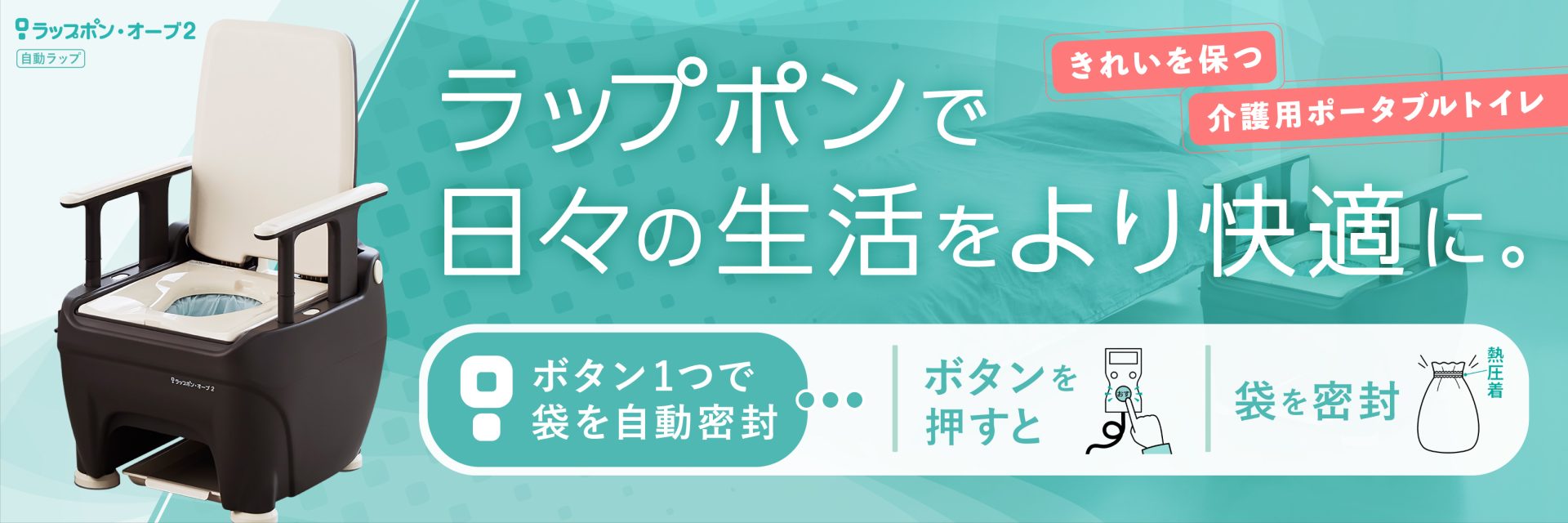住み慣れた自宅で療養したいという願いを叶えるうえで、欠かせないのが介護保険制度における訪問看護サービスです。
訪問看護は、看護師が利用者の自宅を訪問し、医療的なケアや療養上のサポートをしてくれるサービスです。
この記事では、訪問看護の対象やサービス内容を紹介するとともに、サービスにかかる費用と利用までの流れを解説します。
Contents
訪問看護とは
訪問看護とは、病気や障害があり自宅で療養・生活している方の家を看護師が訪問し、必要な医療的ケア、看護、それに関わる処置が提供されるサービスです。
健康状態の悪化防止や回復を目指し、利用者のQOL(Quality of Life=生活の質、人生の質)の向上を狙いとしています。
訪問看護には、介護保険制度を使って提供されるものと医療保険制度で提供されるものの2種類がありますが、この記事では、前者の介護保険制度における訪問看護サービスにスポットを当てて解説します。
訪問看護の対象者(介護保険制度を利用の場合)
訪問看護サービスは次に該当する方を対象としています。
- 要介護認定で要支援1・2、または要介護1~5と判定された方
- 自宅に住み病気や障害によって医療的な処置を必要とする方
- 主治医から訪問看護が必要と認められた方
ただし、介護保険制度を利用できない方は、医療保険制度、または自費で利用することもできます。この場合、要介護認定の有無は問われません。
訪問看護でできること
訪問看護で提供されるサービス内容は次のとおりです。
医療処置・管理
主治医の指示に基づき、看護師が利用者に対して行う医療処置・管理に関するサービスが提供されます。具体的には次のような医療が提供されます。
- 点滴
- 注射
- リハビリテーション
- 痛みの軽減
- 服薬の管理
- 医療機器(例:在宅酸素機器、カテーテル)の管理 など
健康状態の観察・管理
利用者の健康状態を観察し、療養経過を管理します。また、必要に応じて主治医やケアマネジャーなどの専門職に報告します。具体的には次のような内容です。
- バイタルのチェック(血圧、心拍数、脈拍数などの確認)
- 患者の健康状態(顔色、皮膚、認知状態など)の観察
- 床ずれの予防、手当
- 病状悪化の防止・回復 など
療養上の世話・支援
利用者に対する介助や療養上必要とする身の回りの世話や、その他の支援が行われます。
- 食事や排泄などの介助
- 身体の清拭
- 療養生活、健康に関する相談・助言
- 日常生活動作に関する相談、助言 など
ターミナルケア(終末期のケア)
訪問看護では、自宅で最期を迎えようとする方に対してターミナルケアが提供されます。
ターミナルケアとは、終末期に提供される医療のことで、病気などが原因で余命がわずかになった方に対する医療・看護的・介護的ケアを指します。具体的には次のような内容です。
- 終末期にある利用者の食事の介助、オムツの交換
- 苦痛の緩和とそれに伴う看護
- 死に対する不安や恐怖の緩和
- 看取りに伴う看護 など
家族に対する支援
利用者の家族に対して、次のような助言・支援が行われます。
- 日常的な介護方法に関する相談、助言
- 認知症ケアに関する相談、助言
- 看取りを行っている家族への心理的支援 など
訪問看護でできないこと
訪問看護は様々なサービスを受けられるものの、あくまで医療・看護専門のサービスであり、すべてのニーズに対応できるわけではありません。利用者が困惑しやすい、主なできないことについて説明します。
自宅以外での看護
訪問看護は「訪問」を前提としたサービスのため、自宅以外での看護には対応できません。病院や診療所、デイサービスなどの施設での看護は含まれていません。
これは、訪問看護が、自宅での療養生活の支援を前提とした制度であるためです
通院の付き添い
自宅での看護を目的としたサービスのため、訪問看護ステーションのスタッフによる通院の付き添いは、基本的には対応外です。通院が必要な場合は、家族や介護サービス(訪問介護の通院介助や介護タクシーなど)の手配が必要です。
家事全般
訪問看護の対象は医学的ケアに限定されるため、食事の調理、洗濯、掃除などの家事全般には対応できません。これらのサービスが必要な場合は、訪問介護を別途利用する必要があります。ただし、本人の栄養管理に関する指導など、医学的側面からの相談には応じることができます。
医師の指示書がない医療
訪問看護は医師の指示に基づいて実施されるサービスです。医師の指示がない医療行為や薬の変更などには対応できません。利用者側の希望だけでは実現できず、必ず主治医の判断と指示が前提となります。したがって、新たな医療処置が必要になった場合は、まず医師に相談する必要があります。
訪問してくれるのは誰?
訪問看護では、訪問看護ステーションなどの医療機関に所属する下記専門職が利用者の自宅を訪問し、次のサービスを提供します。
| 職種 | 内容 |
| 看護師 | 利用者に対する医療的処置・管理、健康観察と管理、療養上の世話、ターミナルケアを行うとともに、家族に対する支援などを行う。 |
| 理学療法士 | 日常生活における基本動作(起き上がる、立つ、歩く、座る、寝返りをうつなど)に関するリハビリテーションを行う。 |
| 作業療法士 | 日常生活をスムーズに送るための応用的動作(食事、入浴、整容、料理など)に関するリハビリテーションを行う。 |
利用者が必要とする医療の種類、内容、量によって、上記の専門職のいずれかが訪問しサービスを提供してくれます。
訪問看護にかかる費用
介護保険制度を利用する場合、訪問看護サービスでは、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
以下は、一般的な訪問看護ステーションが提供するサービスを利用する際にかかる費用です。
| 専門職 | サービス時間 | 1回あたりの費用 (自己負担額 ※1割の場合) |
| 看護師による訪問 | 20分未満 | 314円 |
| 30分未満 | 471円 | |
| 30分以上1時間未満 | 823円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128円 | |
| 理学療法士・ 作業療法士による訪問の場合 | 20分以上 | 294円 |
出典:「どんなサービスがあるの? – 訪問看護」介護事業所・生活関連情報検索 厚生労働省
訪問看護の利用の流れ
次の流れに沿って、訪問看護サービスを利用します。
主治医に相談
利用者または家族が、主治医(かかりつけ医)に対して、訪問看護サービスを利用したい旨を相談します。その際、訪問看護を利用する理由や、どのような点で医療を必要としているのか伝えると良いです。主治医が「訪問看護の利用が適切である」と認めた場合、次のステップへ進みます。
ケアマネジャーに相談・ケアプランの作成
担当のケアマネジャーに連絡し、訪問看護の利用希望を伝えます。ケアマネジャーは主治医や利用者から事情を聞き、医療的なニーズを十分に把握したうえで、ケアプランのなかに訪問看護サービスを組み入れます。
訪問看護ステーションの選定・契約
訪問看護ステーションを選び、その事業所と契約を交わします。訪問看護ステーションは、インターネットなどで情報収集して自分で探すこともできますが、担当のケアマネジャーに情報収集してもらい、そのなかから評判の良い事業所を選んでもらうのも一つの方法です。
依頼を受けた訪問看護ステーションは、主治医から「訪問看護指示書」を受け取り、ケアプランに沿った訪問看護計画を作成し、サービスが提供できる準備を整えたうえで契約を結びます。
訪問看護を利用
ケアプランに沿って、訪問看護サービスが提供されます。
1回の訪問時間は20分、30分、1時間、1時間半の4区分があり、利用者が必要とする医療の種類、量などによって利用する時間や頻度が異なります。
利用者はサービスの利用回数や訪問時間に応じて費用を支払いますが、介護保険制度が適用されるため、自己負担は1割で済みます(所得に応じて2~3割)。
訪問介護との違い
訪問看護とよく似たサービスに「訪問介護」があります。それぞれの違いを表で説明します。
| 介護保険制度における 訪問看護 | 訪問介護 | |
| 特徴 | 医師の指示に基づき、医療行為が行われる。サービスには家事援助が含まれない。 | 日常生活上の身体介助、家事援助などが提供される。サービスには医療行為は含まれない。 |
| 目的 | 利用者の健康状態の悪化を防止、心身機能の回復のため | 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送るため |
| サービスの 提供主体 | 訪問看護ステーション、医療機関など | 訪問介護サービス提供事業所 |
| 対応する 専門職 | ・看護師 ・理学療法士 ・作業療法士 など | ・ホームヘルパー ・介護福祉士 など |
| 対象者 | 要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と判定された方で、自宅で生活し、主治医から訪問看護が必要と診断された方 | 要介護認定で要介護1~5と判定された方で、自宅で生活する方 |
| サービスの内容 | ・医療処置・管理 ・リハビリテーション ・健康状態の観察 ・服薬管理 ・身体的介助 ・ターミナルケア家族に対する支援 など | ・食事、入浴、排泄の介助 ・掃除、洗濯、調理などの生活援助 ・通院時の外出支援 など |
訪問看護と訪問介護は、専門職が自宅を訪問してサービスを提供してくれる点では共通していますが、それぞれのサービスは目的や特徴が異なります。端的に言えば、両者の違いは医療ケアができるかどうかです。
どちらが自身の希望に合うかどうか分からない場合は、担当のケアマネジャーに確認すると良いでしょう。
なお、訪問介護に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
自宅で安心して介護を受けるには?訪問介護のサービス内容と料金・選び方を解説
よくある質問
ここからは訪問看護に関するよくある質問と、その回答を紹介します。
医療保険と併用できるか
介護保険と医療保険を併用することはできません。
要介護認定を受けていて、主治医が訪問看護が必要と認めた場合は、医療保険よりも介護保険が優先的に適用され、訪問看護サービスが提供されます。
ただし、要介護認定を受けていたとしても重篤な疾患を抱えていたり、難病を患っていたりする場合で、主治医が医療保険制度での利用が適当と判断した場合は、医療保険制度が適用されます。
該当する場合は担当のケアマネジャーに確認しましょう。
訪問してくれる地域・範囲は決まっているのか
おおむね決まっています。
訪問看護ステーションが設置されている地域、またその周辺の地域が、訪問範囲とされているのが一般的です。
なぜなら、サービス内容の性質上、利用者が急変した場合に看護師が駆けつけ十分に対応できるようにするためです。
ただし、訪問看護ステーションによっては、訪問範囲について柔軟に対応できるよう、相談に応じています。詳しくはお近くの訪問看護ステーションや、担当のケアマネジャーに相談してください。
夜間や休日も訪問してくれるのか
ケースによりますが、可能です。
訪問看護ステーションによっては、24時間体制を取っている事業所があります。
この場合、緊急の場合に電話で相談できるだけでなく、利用者の状況によっては、夜間でも看護師などの専門職が駆けつけてくれます。
気になる方は、利用する訪問看護ステーションや担当のケアマネジャーに相談しましょう。
訪問回数に制限はあるのか
介護保険を利用する場合、訪問回数に制限は設けられていません。
実際はケアプランに沿って適切な回数の訪問看護サービスが提供されるため、必要に応じて訪問回数をコントロールすることが可能です。ただし、要介護度に応じて受けられるサービスの量(支給限度額)が決まっているため、それを超えた場合、超過分は介護保険が適用されず、利用者が全額自己負担しなければなりません。
なお、医療保険を使って訪問看護を利用する場合は、通常、週に3回までで、1回の訪問時間は30分~1時間半です。
ただし、患者の抱える疾患やその状態、家族の希望に沿って訪問回数と時間を多少調整することが可能です。
まとめ
この記事では、介護保険制度における訪問看護について、そのサービス内容や費用、そして利用までの流れを解説しました。
訪問看護は、単に医療処置を行うだけのサービスではありません。看護師や専門職が自宅を訪問することで、病状の悪化を防ぎ、日々の健康管理をサポートしてくれます。便利にサービスを活用することで、本人が住み慣れた家で安心して暮らすことができます。
自宅での医療や介護に不安を感じたら、まずはケアマネジャーに相談し、訪問看護をはじめとした介護保険サービスの利用を検討してみてください。
参考文献
- 「訪問看護とは(一般の方向け)」 公益財団法人日本訪問看護財団
- 「訪問看護」厚生労働省老健局 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)
- 「どんなサービスがあるの? – 訪問看護」介護事業所・生活関連情報検索 厚生労働省