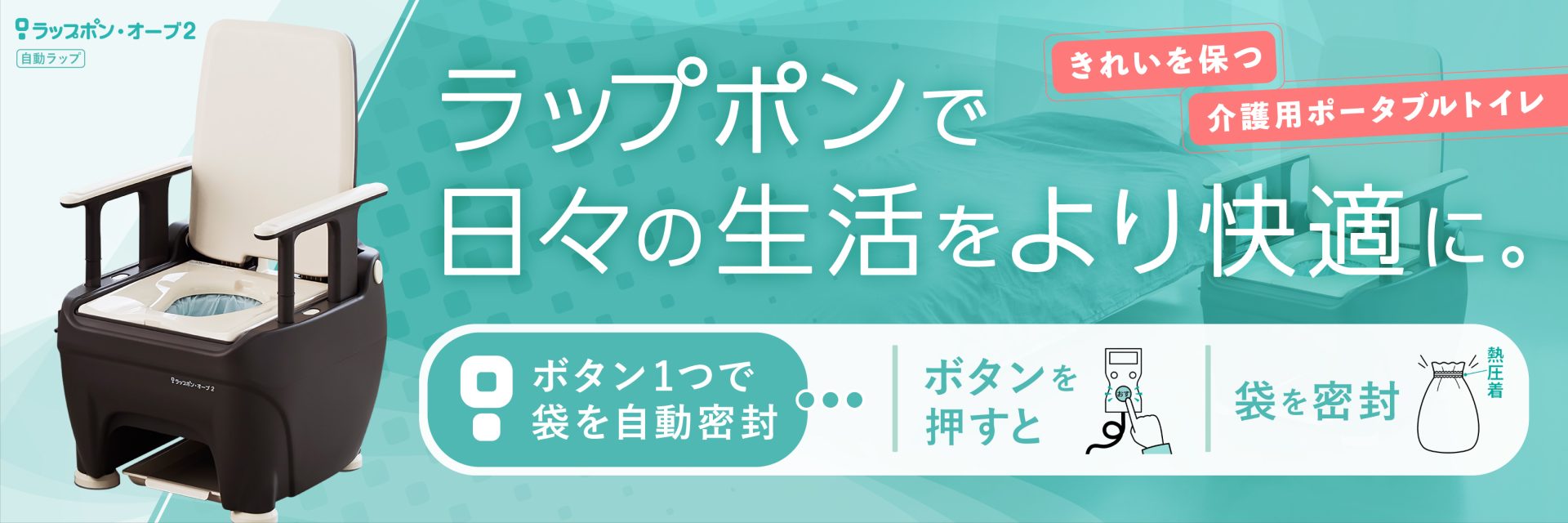「自分たちに介護ベッドは必要?」「使いやすい介護ベッドはどれ?」
介護には介護専用のベッドが必要と聞いて、導入するか悩んでいる方もいるでしょう。
この記事では、介護ベッドが必要な理由や選び方、介護保険の活用方法、補助金などを解説します。
Contents
介護ベッドとは
介護ベッドとは、特殊寝台とも呼ばれる福祉用具です。
電動で背もたれや膝部分の角度を変えられたり、ベッド自体の高さを調整したりする機能があります。
また、サイドレール(柵のような形状をした手すり)が取り付けられる点も一般的なベッドとの違いです。
一般的なベッドではなく介護ベッドが必要な理由
介護ベッドが必要な理由を、利用者側と介護者側の視点でそれぞれ解説します。
利用者側の理由
これまで使用していたベッドや敷布団は高さが固定されており、身体に合わせて調整できません。
そのため、加齢により足腰の筋力が低下している方や関節が動きにくくなっている方は、
立ちあがりにくかったり座るときにバランスを崩したりするリスクがあります。
一方、介護ベッドは身体に合わせて高さを自由に調整できるため、立ち座りがしやすくなります。
また、一般的なベッドや敷布団はつかまるものがなく、起きあがりや寝返りがしにくいです。
介護ベッドはサイドレールが取り付けられるため、自力で起き上がりや寝返りがしやすくなります。
介護ベッドを使用すれば自立した生活を続けやすくなり、介護者に頻繁に頼る申し訳なさも少なくなるでしょう。
なお、介護ベッドの背上げや膝上げの機能を活用すると、ベッドで長時間過ごす方も姿勢を変えやすくなります。
姿勢を変えることで血流がよくなり、床ずれや関節が動きにくくなるリスクを減らせるメリットもあります。
特に、床ずれは一度発症すると治療に時間がかかるため、事前の予防が重要です。
介護者側の理由
一般的なベッドで介助すると、介護者には以下の負担がかかります。
- ベッドの高さが合わず中腰での介助が多くなり、背中や腰を痛めやすくなる
- 車いすや食事などを用意している間に利用者が姿勢を崩さないよう気を配る必要がある
高さを調整できる介護ベッドを使えば、無理な体勢で介助せずにすみます。さらに、利用者の姿勢が安定するため転倒や転落の不安が減り、目の前の介助に集中できるでしょう。
介護ベッドの3つの機能
介護ベッドに搭載されている3つの主な機能を解説します。
背上げ機能
背上げ機能とは、背もたれを好きな高さまで上げられる機能です。
背上げ機能を活用すると利用者は自力で起きあがりやすくなり、介護者の負担軽減にも役立ちます。
また、背上げ機能を使うと利用者はいすに座っているような姿勢となるため、ベッド上での食事やテレビを見るなどの動作もしやすくなります。
膝上げ機能
膝上げ機能とは、利用者の膝部分を持ち上げる機能です。
膝部分を持ち上げることで、背もたれを上げるときに利用者の上半身が足側へずれるのを防げます。
さらに、利用者が横になっているときに膝上げ機能を使って姿勢を変えると血流がよくなり、むくみを防ぐ効果も期待できます。
高さ調整機能
高さ調整機能は、ベッド自体の高さを調整する機能です。
利用者が立ち上がりやすい高さや、介護者が介助しやすい高さなどに自由に調整できます。
就寝時はベッドを低くしておくと、万が一転落してもけがをする可能性を減らせるため安心です。
介護ベッドの種類
介護ベッドは、モーター数に応じて種類が異なります。種類ごとの特徴は以下のとおりです。
| 種類 | 特徴 | おすすめの人 |
| 1モーターベッド | ・背上げ機能、背上げと膝上げが連動する機能、高さ調整機能のうち、どれか1つを搭載 | ・起きあがりや立ち上がりに不安がある人 |
| 2モーターベッド | ・背上げ機能と高さ調整機能、または背上げと膝上げが連動する機能と高さ調整機能を搭載した2つのタイプがある ・どちらのタイプも高さ調整機能は個別に操作可能 | ・自力での起きあがりや立ち上がりが難しく介助が必要な人 |
| 3モーターベッド | ・3つの機能をすべて搭載 ・別々に操作可能 | ・ベッドで長時間過ごす人 ・多くの介助が必要な人 |
| 4モーターベッド | ・3つの機能とマットレスを左右に傾ける寝返り補助機能を搭載 ・別々に操作可能 | ・ベッドで長時間過ごす人 ・多くの介助が必要な人 ・身体の状態に合わせて細かく調整したい人 |
| 1+1モーターベッド | ・背上げ機能と膝上げ機能を搭載 ・別々に操作可能 | ・高さ調整機能が不要な人 |
介護ベッドを選ぶ際に確認する4つのポイント
介護ベッドを選ぶ際に確認するポイントは、機能や種類以外にも4つあります。
介護ベッドの安全性
介護ベッドは身体機能が低下している方が使うため、安全性の高い製品を選びましょう。安全性を確認する方法の一つが、JIS規格(日本産業規格)の表示があるかどうかです。
JIS規格とは、日本の製品やサービスの品質や安全性を全国で統一するために国が定めた基準です。製品と製造工場の両方が審査基準を満たすと、JIS規格の認証が受けられます。
なお、JIS規格の認証を受けている介護ベッドでも、使い方を誤ると事故につながるリスクがあります。取扱説明書を確認し、正しい方法で使用しましょう。
介護ベッドのサイズ
介護ベッドの長さは、主に以下の3種類にわけられます。
| 名称 | 介護ベッドの長さ | 目安となる利用者の身長 |
| ミニ | 約180㎝ | 150㎝未満 |
| レギュラー | 約190㎝ | 150~175㎝ |
| ロング | 約205㎝ | 176㎝以上 |
また、介護ベッドの幅も主に以下の3種類があります。
| 介護ベッドの幅 | おすすめの人 |
| 83㎝ | ・細身の人 ・自力での寝返りができず、介助が必要な人 |
| 91㎝ | ・自力で寝返りができる人 |
| 100㎝ | ・大柄な人 ・自力で寝返りができる人 |
なお、上記は目安であり、介護ベッドの長さや幅はメーカーによって若干異なります。
一般的なシングルベッドの幅は約100㎝ のため、介護ベッドは一般的なベッドよりも幅が狭く設計されています。
ベッドの幅が狭いメリットは以下の2つです。
- 利用者と介助者の距離が近くなり、介助しやすい
- 狭い部屋でも介護者の動線を確保しながらベッドを設置できる
ベッドでリラックスして過ごすことを大切にしたい方は、幅が広めのベッドを選ぶとよいでしょう。
必要な付属品
介護ベッドを安全に使用できるよう、手すりやテーブルなどの付属品が必要か検討しましょう。付属品の種類は豊富なので、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員などの専門家と相談しながら利用者に合うものを選ぶのがおすすめです。
なお、サイドレールは介護ベッドから利用者が転落するのを防げるため、設置しておくと安心です。
ただし、サイドレールは介護ベッドに差し込まれているだけであり、しっかりと固定されていません。手すりが必要な場合は、介護ベッドにしっかり固定できる介助バーを選ぶとよいでしょう。
マットレスの種類
介護ベッドのマットレスは製品によって特徴が異なります。
例えば、低反発ウレタンマットレスは適度に身体が沈み込むため、寝心地を重視したい方におすすめです。
一方、高反発ウレタンマットレスは身体が沈み込みにくく、寝返りや立ち上がりなどがしやすいです。
横になっている時間が長い方が使用する場合は、床ずれを予防するために体圧分散性能が高いマットレスを選びましょう。
さらに、快適に使えるマットレスを選ぶために、撥水加工や抗菌加工、通気性、お手入れ方法なども確認しておくのがおすすめです。
介護保険で介護ベッドをレンタルできる条件
介護保険で介護ベッドをレンタルできるのは、原則要介護2以上の認定を受けている方です。
ただし、要支援や要介護1の方も以下のいずれかの条件に該当すれば、例外的に介護保険を利用できます。
- 日常的に起きあがりが困難な者
- 日常的に寝返りが困難な者
また、医師の所見や利用者・家族・専門職が参加するサービス担当者会議の結果を踏まえて市町村が必要と判断した場合も、例外的に介護保険でレンタルできます。
条件に当てはまるか判断するのは難しいため、まずはケアマネジャーに相談しましょう。
なお、介護ベッドを購入する際は介護保険サービスが適用されないため、全額自己負担となります。
介護保険を利用したレンタルの流れや料金などの詳細は「福祉用具貸与で安心介護!レンタルできる福祉用具の種目と利用の流れ」をご覧ください。
出典:要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について 厚生労働省
介護ベッド導入時に活用できる補助金制度
介護ベッドを導入する際に利用できる補助金制度は、介護保険以外にも3つあります。
自治体独自の補助制度
自治体によっては、介護保険でレンタルできる条件を満たしていない方でも無料または通常より安価で介護ベッドを借りられる独自の制度があります。
なお、対象者や貸し出し期間、使用料などは自治体によって異なります。詳細を知りたい場合は、役所に問い合わせてみましょう。
民間の介護保険
民間の介護保険には、介護が必要になった際に一時金を受け取れる保険があります。一時金は用途が決まっていないため、介護ベッド導入の費用に充てられます。
民間の介護保険に加入している場合は、保障内容を確認してみましょう。
日常生活用具給付
日常生活用具給付とは、障がい者が自立した日常生活を送るために必要な用具の購入やレンタルを公費で助成する制度です。対象となる用具には介護ベッドも含まれています。
申請の流れや給付の上限額などは市町村によって異なるため、役所に確認しましょう。
なお、介護保険の対象者が介護ベッドを導入する場合は、日常生活用具給付よりも介護保険サービスが優先されます。
介護ベッドを使用する際の注意点
介護ベッドを安全に使用するための注意点を3つ解説します。
利用者が挟まりそうな隙間をなくす
マットレスとサイドレールの間に隙間があると、利用者の手足が挟まってしまうことがあります。介護者が気付かずに背上げや膝上げをしてしまうと、事故につながる危険性があります。
隙間をなくすために、マットレスとサイドレールの間をクッションやタオルなどで埋めましょう。
なお、2009年のJIS規格改正前のサイドレールは、サイドレール自体の隙間やサイドレール同士の隙間に利用者の手足や頭などが挟まる可能性があります。そのため、JIS規格改正後のサイドレールを選ぶようにしましょう。
手元スイッチの置き場所を決めておく
手元スイッチ(リモコン)の置き場所を決めておかないと、思わぬ誤操作が起こる可能性があります。
認知症の方が誤って背もたれやベッドの高さを調整してしまうと、介護ベッドから転落してしまうかもしれません。また、介助後に手元スイッチをベッド上に置きっぱなしにしてしまうと、利用者の身体が当たり介護ベッドが動くこともあります。
介護者が複数人いる場合は、手元スイッチの置き場所を共有しておきましょう。利用者が手元スイッチを誤操作してしまう可能性があるなら、利用者の手が届かない場所や見えない場所で保管するのがおすすめです。
背もたれを上げる際は腰の位置に注意する
背もたれを上げる際は、ベッドが動く部分と利用者の腰の位置が合うようにしましょう。腰の位置が合っていないと利用者の姿勢が不自然になり、負担がかかります。膝上げ機能を使ってから背もたれを上げると、腰の位置がずれにくいです。
腰の位置を合わせると利用者の膝と膝上げ部分の位置が合わなくなる場合は、枕やクッションを利用者の足とベッドの間に挟んで調整するようにしましょう。
まとめ
介護ベッドには角度や高さを調整する機能があり、一般的なベッドで介助するときの不便さや負担を軽減できるベッドです。介護ベッドを導入する際は、機能や安全性、介護保険が活用できるかなど確認するポイントがたくさんあります。
ケアマネジャーや福祉用具専門相談員などの専門家に相談しながら、利用者と家族が安心して使える介護ベッドを探しましょう。
参考文献
- 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案」 厚生労働省
- どんなサービスがあるの?‐福祉用具貸与」介護事業所・生活関連情報検索 厚生労働省
- 要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」 厚生労働省
- 車いす・介護用ベッドの貸し出し(短期)」 練馬区
- 日常生活用具給付等事業の概要」 厚生労働省
- JIS T9254:2009」 厚生労働省
- 医療・介護ベッド安全点検チェック表」 厚生労働省