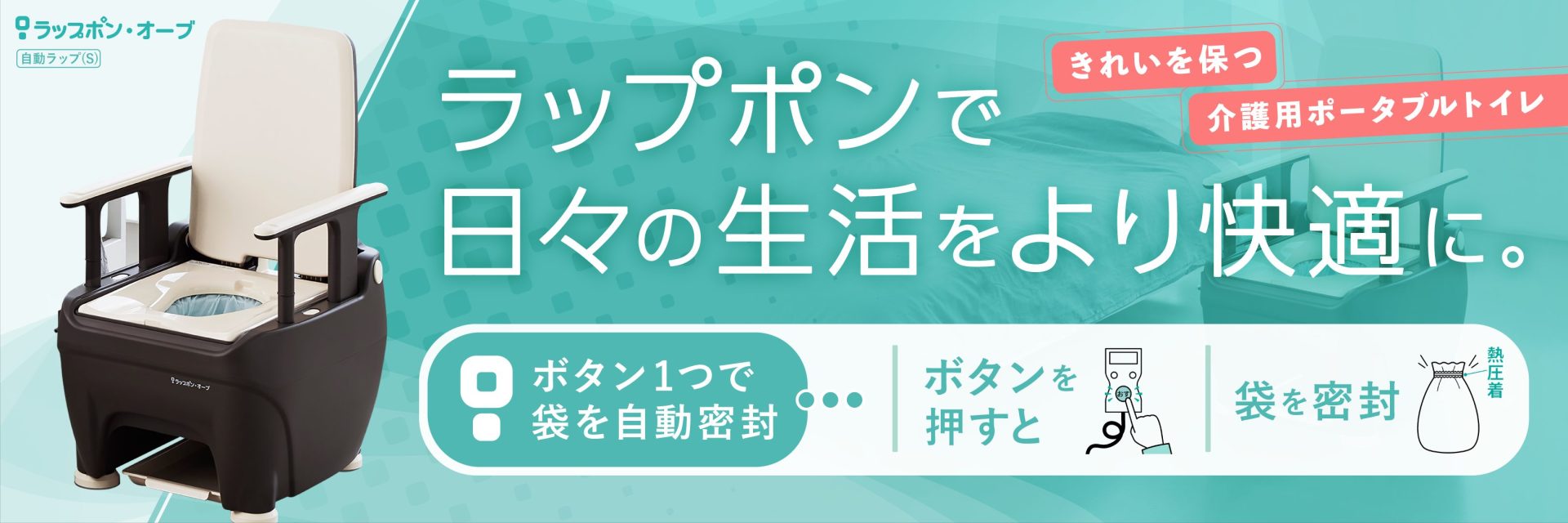「使いやすい車いすはどれ?」「介護保険を利用して車いすをレンタルできる?」
家族のために車いすが必要になったけれど、選び方や使い方がわからず困っている方もいるでしょう。
この記事では、車いすの種類や選び方、介護保険を使ったレンタル方法、介助の際の注意点などを解説します。
「使いやすい車いすはどれ?」
「介護保険を利用して車いすをレンタルできる?」
家族のために車いすが必要になったけれど、選び方や使い方がわからず困っている方もいるでしょう。
この記事では、車いすの種類や選び方、介護保険を使ったレンタル方法、介助の際の注意点などを解説します。
Contents
介護保険を利用して車いすをレンタルするメリット
車いすは購入・レンタルどちらも可能ですが、介護の場合はレンタルして使う人の方が多い傾向にあります。それはなぜなのか、ここでは車いすをレンタルするメリットを紹介します。
費用を抑えることができる
介護保険を利用すれば、車いすのレンタル費用を大幅に抑えることができます。介護保険の福祉用具貸与サービスでは、レンタル料金の1割から3割の自己負担で車いすを借りることが可能です。
車いすを購入する場合、一般的なもので数万円、高機能なものだと20万円以上かかることもあります。しかし、レンタルなら月額数百円から数千円程度の負担で利用できるため、経済的な負担を大きく軽減できます。(詳細は後述)
また、レンタル料金には定期的なメンテナンス費用も含まれています。(基本的なメンテナンスは無料ですが、各種パーツ代やメンテナンス内容によっては有償になることがあります。)
専門家に相談できる
介護保険で車いすをレンタルする際は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員といった専門家のサポートを受けられます。これは介護初心者の方にとって非常に心強いメリットです。
ケアマネジャーは利用者の身体状況や生活環境を総合的に判断し、最適な福祉用具の選定をサポートします。また、福祉用具専門相談員は車いすの種類や機能について詳しく説明し、実際の使い方や安全な操作方法も指導してくれます。
車いすには標準型、リクライニング型、電動型など様々な種類があり、初めての方が自分で選ぶのは困難です。専門家のアドバイスを受けることで、利用者の身体状況や使用目的に最も適した車いすを選ぶことができ、安全で快適な介護生活を実現できます。
身体状態の変化に応じて商品を変えられる
レンタルの大きな利点は、利用者の身体状態の変化に応じて柔軟に車いすを交換できることです。介護が必要な方の身体状況は時間とともに変化することが多く、その都度適切な福祉用具に変更する必要があります。
例えば、当初は自走式の標準型車いすで問題なくても、身体機能の低下により介助式やリクライニング型が必要になることがあります。購入した場合は買い替えに再び高額な費用がかかりますが、レンタルなら比較的簡単に交換できます。
介護保険を利用して車いすをレンタルする条件
介護保険を利用して車いすをレンタルできるのは、原則要介護2以上の認定を受けている方です。ただし、要支援や要介護1の方でも、以下のいずれかに当てはまる場合は介護保険によるレンタルが例外的に認められます。
- 日常的に歩行が困難な者
- 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
また、医師の所見やサービス担当者会議(利用者・家族・専門職が参加する話し合い)の結果をもとに市町村が必要と認めた場合も、介護保険を利用してレンタルできます。
出典:要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について 厚生労働省
介護保険を利用して車いすをレンタルする場合の料金
車いすのレンタルは、介護保険の福祉用具貸与のサービスを利用できます。原則1割の自己負担額で借りられますが、利用者の所得によっては2〜3割となることもあります。
以下は、介護保険適用外と適用時の月額レンタル料金(1割負担)の目安です。
| 車いすの種類 | 介護保険適用外の料金 | 介護保険適用時の料金 |
| 自走式車いす | 約3,000~8,000円 | 約300~800円 |
| リクライニング・ティルト車いす(一体型) | 約8,000~16,000円 | 約800~1,600円 |
| 電動車いす(標準型) | 約26,000~30,000円 | 約2,600~3,000円 |
なお、車いすのレンタルは費用面だけでなく、定期的なメンテナンスや身体の状態に合わせた借り換えなどのメリットもあります。
購入する場合の料金
車いすはレンタルだけでなく、購入することも可能です。
車いすを購入すると傷や汚れを気にせず使用できますが、介護保険を利用できないため全額自己負担となります。以下は、購入時の値段の目安です。
| 車いすの種類 | 値段 |
| 自走式車いす | 約17,000~31,000円 |
| リクライニング・ティルト車いす(一体型) | 約85,000~170,000円 |
| 電動車いす(標準型) | 約200,000~500,000円 |
車いすを購入するためにはまとまった費用が必要ですが、長期的に使用するならレンタルより安く済むこともあります。利用頻度やレンタル期間を踏まえて、どちらが安くなるか検討しましょう。
介護保険を利用して車いすをレンタルするまでの流れ
介護保険の福祉用具貸与を利用して車いすをレンタルする流れは、以下のとおりです。
1.介護保険を申請し、要介護認定を受ける
2.ケアマネージャーにケアプランを作成してもらう
3.レンタルする業者を選ぶ
4.レンタルする車いすを決め、契約する
5.レンタルを開始する
介護保険の申請や車いすの選定は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員(福祉用具の選び方や使い方などをアドバイスしてくれる専門職)などがサポートしてくれます。利用者や家族だけで悩まずに専門家へ相談することで、スムーズに車いすをレンタルできるでしょう。
福祉用具貸与の詳細については、「福祉用具貸与で安心介護!レンタルできる福祉用具の種目と利用の流れ」をご覧ください。
介護で使用する車いすの種類
介護で使用する車いすは主に5種類あります。それぞれの特徴を解説します。
自走式車いす
自走式車いすとは、利用者自身が操作して動かせる車いすです。後輪が大きいため安定感があり、小さな段差があっても進みやすいです。
一般的には、後輪の外側についているハンドリム(手でタイヤを回すための輪)を使って車いすを操作します。また、利用者が足で地面を蹴って動かす場合もあります。
なお、自走式車いすにも背もたれの上部に手押しハンドルがあるため、介助者が後ろから押すことも可能です。
介助式車いす
介助式車いすは、利用者ではなく介助者が押して動かす車いすです。後輪が自走式車いすよりも小さく、タイヤを操作するためのハンドリムもついていません。
後輪が小さいぶん狭い場所で使用しても小回りが利き、折りたたむとコンパクトになるため収納もしやすいです。さらに、比較的軽いものが多く、持ち運びやすい点も介助式車いすの特徴です。
モジュール車いす
モジュール車いすとは、利用者に合わせて各パーツを調整できる車いすです。調整できるパーツは、車いすによって異なります。
以下は、調整できる主なパーツの例です。
- 座面の幅や高さ
- アームサポート(肘掛け)の高さ
- フットサポート(足置き)の高さ
- 背もたれの高さや角度
利用者の身体の状態が変化しても再調整できる点が、モジュール車いすのメリットです。さまざまな利用者に合わせられるため、介護施設でもよく使われています。
リクライニング・ティルト車いす
リクライニング・ティルト車いすは、標準的な形の車いすでは座位を保つのが難しい方でも利用しやすい車いすです。
リクライニング車いすは、背もたれを倒して角度を変えられます。お尻にかかる体圧を背中や太ももへ分散でき、利用者も疲れにくいです。ただし、お尻が前へ滑りやすいという注意点があります。
一方、ティルト車いすは座面と背もたれの角度を保ったまま後ろへ傾けられるため、お尻が前に滑りにくいです。リクライニング車いすと同様に、お尻にかかる体圧の分散効果もあります。
なお、リクライニングとティルトの両機能があり、利用者に合わせて座面や背もたれの角度を調整できる車いすもあります。
電動車いす
電動車いすとは、電動モーターで動く車いすを指します。利用者の負担が少なく、自力で車いすをこぐのが難しい方でも使いやすいです。
電動車いすには標準的な形の車いすに電動モーターが搭載されている標準型や、スクーターのような形状をしているハンドル型(電動カート)などがあります。どの電動車いすも歩行者扱いとなるため、運転免許証がなくても屋外走行が可能です。
なお、電動車いすには介助者の負担を軽減する介助用もあります。少ない力で押せたり、下り坂で自動ブレーキがかかったりなど、介助者が疲れにくい機能が搭載されています。
利用者が使いやすい車いすの選び方
利用者が使いやすい車いすを選ぶ3つのポイントを解説します。
利用者の身体のサイズに合わせる
車いすを選ぶ際は、利用者の身体のサイズに合っているか確認しましょう。以下に、確認するとよい点をまとめました。
| 確認する箇所 | ポイント |
| 座面の幅 | ・お尻の幅+約3~5㎝ |
| 座面の高さ | ・ひざ下からかかとまでの高さ+約5〜8㎝(利用者が足でこぐなら+約0~2㎝)・座面にクッションを敷くなら厚みを差し引く |
| 座面の奥行き | ・お尻の後ろの端から膝裏までの長さ-約5~7cm |
| アームサポートの高さ | ・座って肘を無理なく曲げた位置が目安・食卓や机などの高さも考慮する |
| 背もたれの高さ | ・自走できるなら肩甲骨の下あたり |
利用者の身体のサイズに合った車いすを選ぶと乗り心地が良く、長時間でも快適に使用できます。さらに、転倒や車いすからの転落、床ずれなどのリスクも減らせます。
なお、介助者が押しやすい高さに手押しハンドルがあるかも確認しておきましょう。
利用者の身体の状態に合わせる
利用者の身体の状態によって、使いやすい車いすは異なります。
例えば、自分の手や足で車いすを動かす体力がある方は、自走式車いすがおすすめです。一方、自分で車いすを操作できますが自走する体力がない方は、電動車いすが使いやすいです。
自分で操作ができない方は、姿勢を保てるなら介助式車いす、姿勢が保てないならリクライニング・ティルト車いすを選びましょう。
使用する環境に合わせる
車いすを選ぶ際は、使用する環境も考慮しましょう。以下は、使用する環境に合わせた車いす選びの具体例です。
- 狭い室内で使用するなら小回りが利く車いす
- 屋外での使用が多いなら段差があっても進みやすく乗り心地がよい車いす
- 持ち運びが多いなら軽くてコンパクトにたためる車いす
使用する環境を具体的に想像し、どのような車いすなら利用者も介助者も使いやすいか考えてみましょう。
車いすのパーツ別確認ポイント
車いすは同じ種類であっても、パーツの違いで使いやすさや乗り心地が異なります。ここからは、パーツ別の確認ポイントを解説します。
タイヤの種類
車いすのタイヤは、エアタイヤとノーパンクタイヤの2種類があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
| タイヤの種類 | 特徴 |
| エアタイヤ | ・空気を入れて使用する・空気がクッションとなるため乗り心地がよい・空気圧の確認や空気入れなど定期的なメンテナンスが必要 |
| ノーパンクタイヤ | ・空気ではなく樹脂が中に入っている・空気を入れる必要がないため、定期的なメンテナンスは不要・乗り心地はエアタイヤより劣る・比較的重く、購入時や交換時の値段が高め |
なお、中にスポンジ状の素材を入れ、乗り心地が改善されているノーパンクタイヤもあります。
車輪のサイズ
車輪のサイズによって、車いすの使いやすさは異なります。
例えば、車輪のサイズが大きいと段差を乗り越えやすいため、安全性が高いです。さらに、ひとこぎで進む距離が長く、少ない力で移動できます。
一方、車輪のサイズが小さいと小回りが利くため、狭い室内や人ごみでも使いやすいです。
フレームの素材
車いすは使用されているフレームの素材によって、耐久性や重量などが変わります。一般的には、比較的軽く強度も強いアルミ製フレームが使用されています。
スチール製フレームは重量がありますが、頑丈で耐久性が高いです。比較的安価で購入できるため、介護施設や病院などでよく使われています。
車いすの方を介助する際の注意点
ここからは、安全に車いすの方を介助するための注意点を3つ解説します。
車いすを利用する前に必ず点検する
車いすを利用する前に、必ず以下を点検しましょう。
- ブレーキはかかるか
- タイヤの空気は入っているか
- 車輪がスムーズに動くか
- ねじがゆるんでいるところはないか
- 壊れているところはないか
事前に車いすを丁寧に点検することで、転倒や転落などの事故を防げます。
動作の前に利用者へ声をかける
車いすを動かすときや止まるとき、段差を越えるときなど、何かしらの動作をする前には利用者へ声をかけましょう。急に動いたり止まったりすると、利用者は安心して車いすに乗れません。
「今から右に曲がりますね」「これから坂道を上りますよ」など、今後どのように動くのか利用者にもわかるような声をかけましょう。
段差や急な坂道は後ろ向きで降りる
段差や急な坂道は、後ろ向きで降りたほうが安全です。前向きで降りると、利用者が転がり落ちてしまう恐れがあります。
なお、車いすを後ろ向きにして降りるのは利用者に不安を与えます。不安を取り除くためにも、声かけをしてから介助しましょう。
まとめ
車いすは自走式や介助式などさまざまな種類があり、機能や値段が異なります。そのため、利用者の身体の状態や使用環境などに合わせて車いすを選ぶことが大切です。
ケアマネジャーや福祉用具専門相談員などに相談しながら、利用者と介助者が使いやすい車いすを見つけましょう。
参考文献
「どんなサービスがあるの?‐福祉用具貸与」介護事業所・生活関連情報検索 厚生労働省