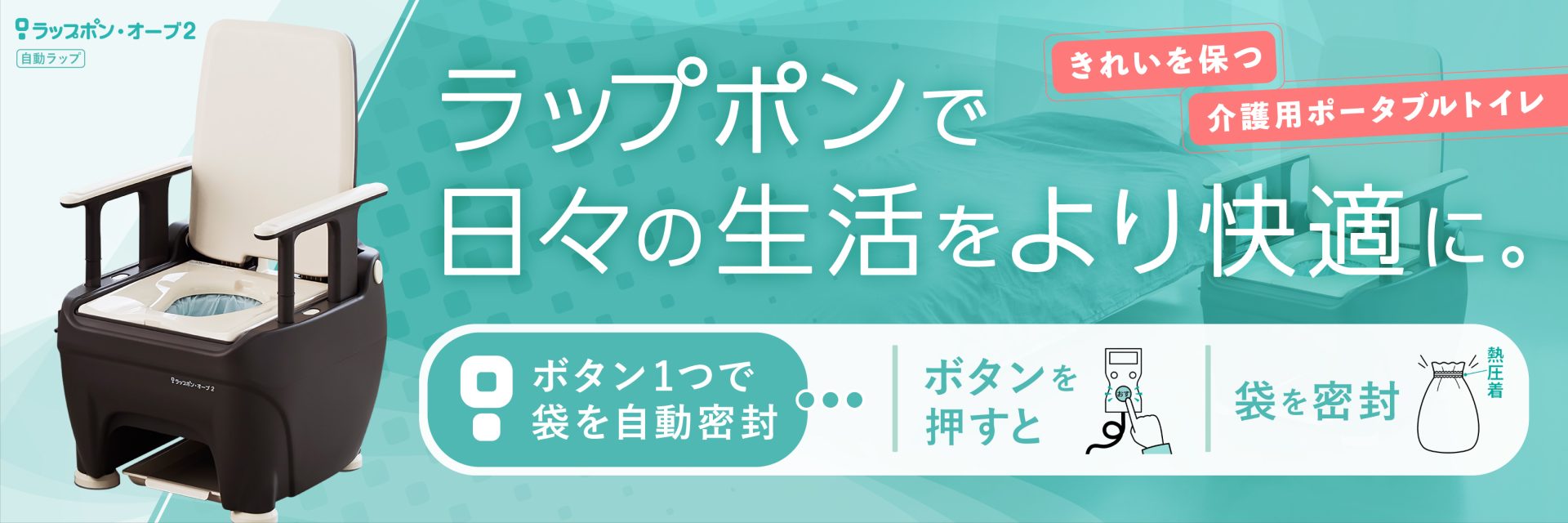「使いやすい介護用手すりはどれ?」「介護用手すりを設置するときの費用はいくら?」
家族のために手すりを設置したいけれど、選び方や費用がわからず不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、介護用手すりの役割や選び方、介護保険を使った設置方法などを解説します。
介護用手すりについての理解が深まり、家族が安心して生活できる環境を整えていくための参考になれば幸いです。
Contents
介護用手すりの3つの役割
介護用手すりは、高齢者が安心して生活を送るための重要な役割を3つ担っています。それぞれの役割を詳しくご紹介します。
歩行のサポート
介護用手すりの役割の一つは、利用者の歩行のサポートです。
高齢者のなかには、筋力の低下や病気による麻痺などが原因で歩くのが難しい方がいます。手すりによって身体にかかる負担が分散され、自力で歩くのが不安な方でもバランスを取りやすくなります。
また、手すりがあると暗くて見えにくい夜間の歩行も安心です。
日常的な動作のサポート
介護用手すりは、起き上がりや立ち上がり、姿勢の保持などをサポートする役割があります。
ベッドからの起き上がりやトイレに座るなどの日常的な動作でも、高齢者にとっては負担が大きいです。手すりを活用すれば負担を軽減でき、利用者も自立して行動しやすくなります。
転倒・転落の防止
転倒・転落の防止は、介護用手すりの大切な役割です。
転倒や転落が原因で高齢者がけがをすると、自力での歩行が難しくなり、車いす生活になる恐れがあります。介護用手すりがあれば転倒や転落の可能性を減らせるため、高齢者も安心して生活できます。
よく使われる手すりの種類
よく使われる手すりについて、それぞれの種類ごとに解説します。
工事が不要タイプ
工事が不要タイプは、手軽に設置できる手すりです。布団やソファの横といった必要な場所へすぐに設置できる点が魅力です。以下の2種類がよく使われます。
| 種類 | 特徴 |
| 据え置き型 | ・床に置いて使用する ・土台部分にさまざまな形の手すりが取り付けられている |
| 突っ張り型 | ・床と天井の間に突っ張り棒のように設置する ・使用時は上のほうを持って身体を引っ張りあげる |
なお、両方とも屋外で使用できるタイプもあります。玄関前の階段や車庫までの通路などに設置すると、利用者が安心して外出しやすくなります。
工事で取り付けるタイプ
工事で取り付けるタイプは、壁や柱などに直接取り付ける手すりです。主に使われる形状は、以下の3種類です。
| 手すりの形状 | 特徴 |
| 水平型手すり | ・横向きに取り付ける ・つかみながら歩ける ・トイレや玄関などでの姿勢保持に役立つ |
| 縦型(I型)手すり | ・縦向きに取り付ける ・立ち座りや段差の上り下りなどを補助する ・扉を開閉する際の姿勢保持に役立つ |
| L字型手すり | ・水平型手すりと縦型手すりが一体型になっている ・トイレや浴室などで立ち上がりや姿勢保持に役立つ |
取り付けタイプの手すりは工事が必要ですが、しっかりと壁や柱に固定するため、他の手すりよりも強度が高いです。
手すりの選び方
手すりを選ぶポイントは3つあります。ポイントを理解し、利用者が使いやすい手すりを見つけましょう。
利用者の身体の状況や動作に合わせる
手すりを選ぶ前に、利用者の身体の状況や動作を観察しましょう。
利用者が使いにくい手すりでは、安全を守るための役割を果たせません。どのような形状の手すりをどこに設置すれば利用者が安心して過ごせるか考えることが大切です。
なお、介護施設では介護士や看護師、リハビリの専門職などが連携して必要な支援方法を検討します。自宅で手すりの設置を検討する際も、ケアマネジャーやかかりつけ医、福祉用具事業者などに相談するのがおすすめです。
利用者に合わせて高さや太さを決める
人によって体格や麻痺の程度などに差があるため、利用者が使いやすい高さに合わせて手すりを設置しましょう。利用者の不在時に高さを決めてしまうと、使いにくい位置に設置してしまう恐れがあります。
手すりの太さは、握ったときに指先が触れる程度が目安です。握るのが難しい場合は、手のひらやひじを乗せられる平らな形状を選びましょう。
使いやすい素材にする
利用者が安心して手すりを利用するためには、使用する環境に合った使いやすい素材を選ぶ必要があります。
例えば、ステンレス製の手すりを屋外に設置すると日光で熱くなるため、利用者が触りにくくなります。また、浴室に設置する場合は、滑り止めや防水の加工が施されている手すりが使いやすいです。
手すりを取り付ける場所別の設置ポイント
トイレや階段など、手すりを取り付ける場所によって注意する点が異なります。ここからは、手すりを設置する主な場所別のポイントを解説します。
トイレ
トイレは便座からの立ち座りをするため、縦型やL字型の手すりがあると便利です。
手すりを取り付ける位置は、便座から立ち上がったときに利用者よりも前にくるようにしましょう。立ち上がった際に手すりが後ろにあると、肩に負担がかかります。
さらに、以下の2点も確認しておくと、手すりを設置したあとに不便さを感じにくくなります。
- ペーパーホルダーやウォシュレットのリモコンが使いにくくならないか
- 介助者が一緒に入れるスペースを確保できるか
なお、座位が不安定な方は、排泄時の姿勢を保持する手すりも設置すると安全性が高まります。
階段
階段は上り下りによって利き手側が変わるため、可能であれば両側に手すりを設置しましょう。幅が狭い場合は、下りるときの利き手側に取り付けるのが基本です。
階段の始まりと終わりの部分は、20cmほど水平型手すりも設置しておくと最後まで身体を支えられます。上りきったところに壁がない場合は、縦型手すりを設置すると身体を引き上げやすくなります。
廊下
廊下の手すりの高さを測る際は、大転子(足の付け根にある骨が出っ張った部分)やまっすぐ腕をおろしたときの手首の位置が参考になります。いずれの方法で測っても、約75〜80cmになるのが一般的です。
廊下の途中に窓やふすまがある場合は、突っ張り型とバータイプの手すりを組み合わせると途切れずに手すりを設置できます。
玄関
玄関に上がりかまち(靴を脱ぎ履きする土間と室内の床との段差部分)がある場合、縦型の手すりがあれば段差を上り下りしやすくなります。上がりかまちやいすに座って靴を履く方は、L字型手すりを設置すると立ち上がりから歩行へスムーズに移れます。
なお、段差がない、または段差が低い玄関は上り下りの負担が少ないです。そのため、歩行をサポートする水平型や斜め型(壁に対して斜めに取り付ける手すり)も使いやすいです。
介護保険を使って手すりを設置する2つの方法
介護保険を使って手すりを設置する方法は2つあります。それぞれの特徴や費用を解説します。
住宅を改修して取り付ける
住宅改修して手すりを取り付ける場合は、介護保険の「住宅改修制度」のサービスが受けられます。手すりの取り付け工事にかかった費用の1〜3割が自己負担額となり、支給限度額は20万円です。
例えば、手すりを取り付ける工事費用が10万円であれば、自己負担額は1〜3万円となります。残りの7〜9万円の支払い方法は、自治体によって異なります。
住宅改修制度の詳細については、「介護保険の住宅改修でできることとは?流れやレンタルについても解説」をご覧ください。
手すりをレンタルする
介護保険の「福祉用具貸与」を利用すると、据え置き型と突っ張り型の手すりをレンタルできます。
レンタルにかかる自己負担額は、通常価格の1〜3割です。例えば、月額4,000円の手すりを選んだ場合、400〜1,200円でレンタルできます。
なお、介護保険は要介護度によって1ヶ月の支給限度額が決まっています。福祉用具貸与と他サービスを組み合わせた費用が限度額内に収まるよう、ケアマネジャーと相談しましょう。
介護保険制度の詳細については、「介護保険ってなに?初めて介護する人が知っておくべきこと」をご覧ください。
介護保険で手すりを設置する流れ
介護保険で手すりを設置する流れは、工事による取り付けかレンタルかによって異なります。
まず、工事による取り付けの流れをご紹介します。
1:要介護認定を受ける
2:ケアマネジャーへ相談する
3:工事を依頼する業者を選ぶ
4:必要書類を市区町村へ提出
5:申請が承認されたら工事を開始する
6:工事費用を業者へ支払う
7:市区町村へ給付申請する
8:給付金が支給される
次に、レンタルの流れです。
1:要介護認定を受ける
2:ケアマネジャーへ相談し、ケアプランを作成してもらう
3:レンタル業者を選ぶ
4:福祉用具専門相談員が利用者の自宅へ訪問し、手すりを選定する
5:ケアマネジャーへ連絡し、レンタル業者と契約する
6:レンタルサービスを開始する
福祉用具専門相談員とは、利用者に合った福祉用具をアドバイスしたり利用計画書を作成したりする専門職です。レンタル開始後も定期的に利用者の自宅を訪問し、メンテナンスや使い心地の確認をしてくれます。
介護保険で手すりを設置する際の注意点
介護保険で手すりを設置する際の注意点を4つ紹介します。注意点をあらかじめ知っておくと、スムーズに手すりを設置できるでしょう。
介護保険を申請してから業者へ依頼する
介護保険を活用するためには、手すりを設置する前に介護保険を申請する必要があります。手すりを設置してから介護保険を申請しても、サービスは受けられません。
なお、申請に必要な書類の作成といった事務手続きを家族のみで行うのは手間がかかります。ケアマネジャーや福祉用具事業者などと連携しながら進めましょう。
手すりを取り付けられるか確認する
壁材によっては、住宅改修で希望する手すりが取り付けられないことがあります。家族だけで工事できるか判断するのは難しいため、業者に確認してもらいましょう。
特に、福祉住環境コーディネーター(2級以上)の有資格者がいる業者であれば、家屋の構造や福祉の知識などを踏まえて適切なアドバイスをしてくれます。
なお、介護保険を使って手すりを設置できるのは、原則利用者の自宅のみです。子どもの家に一時的に居候しており住民票を移していない場合は、手すりを設置しても給付対象外となります。
また、自宅が賃貸の場合、取り付け工事をするためには大家の許可が必要です。
自治体の補助金制度があるか調べる
自治体によっては、手すりを設置する際に介護保険だけでなく、独自の補助金制度も利用可能です。
例えば、大阪市には高齢者住宅改修費給付事業という独自の制度があります。制度を利用すると、手すりの取り付けと同時に行う住宅改修対象外の工事にも補助金が出ます。
補助金の対象者や申請方法は自治体によって異なるため、手すりを設置する前にケアマネジャーへ確認しましょう。
複数の業者から見積もりを取る
業者によって工事費用やレンタル費用が異なるため、複数の業者から見積もりを取りましょう。
また、見積もりを依頼する際に介護保険を利用した手すりの設置に詳しいかどうかも聞いておくのがおすすめです。介護保険サービスに詳しい業者を選ぶと、申請の流れや必要書類などを把握しているため安心して任せられます。
業者選びに迷った際は、ケアマネジャーへ相談しましょう。
まとめ
介護用手すりは、利用者の日常的な動作のサポートや転倒・転落の防止など、重要な役割を担っています。本人の身体状況や使用環境などを踏まえて、使いやすい手すりを選ぶことが大切です。
介護保険サービスも活用しながら、家族が安心して暮らせる環境を整えていきましょう。
参考文献
「高齢者のための住宅改修ポイント【ポイント2】」 広島県
「どんなサービスがあるの? – 福祉用具貸与」介護事業所・生活関連情報検索 厚生労働省
「福祉用具・住宅改修」 厚生労働省
「高齢者住宅改修費給付事業」 大阪市